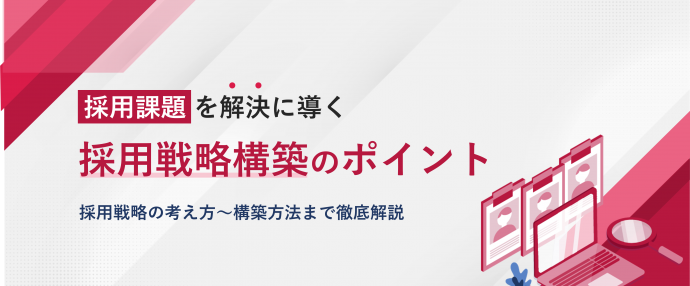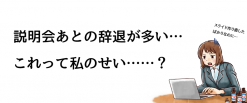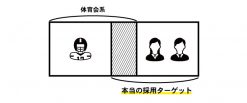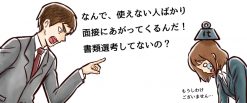そもそも採用基準とは?
採用基準とは、自社にマッチする人材を採用するための評価指標を指します。求職者の行動特性や価値観など、履歴書やエントリーシートからは見えない部分の評価を判断する重要な指標です。きちんとした採用基準を設けることで、自社の採用活動を活性化し、より効率よく人材を採用できます。その重要性や目的、メリットなどはこのあとの章で解説します。
採用基準の重要性・目的
採用基準は属人的・感情的な評価によって合否に悪影響が出るのを防ぐのに有効です。ここでは、その重要理由について解説します。
選考の属人化を防ぐ
明確な採用基準があれば、採用担当者が離職したり、選考プロセスごとに面接官が異なる場合でも評価を統一できるようになり、選考の属人化防止につながります。
採用基準がない場合、面接官によって「よい」と思うポイントが異なり、採用する人材の質にばらつきが出てしまいます。たとえば、人材要件に合致している人材であるにも関わらず、面接官の受けた印象だけで、面接が不得手な応募者を不採用にしてしまう可能性があります。反対に、面接での会話が得意で好印象な応募者であっても、スキル面では要件を満たしていないかもしれません。
入社後のミスマッチを防ぐ
明確な採用基準は、自社の業務に必要なスキルや経験を持っているか、自社の社風に合うかを見極めやすくなり、入社後のミスマッチ防止に効果的です。
採用基準が曖昧だと、たとえば、学歴や職歴だけを見て採用してしまい、能力はあっても職場環境に馴染めず早期離職する社員が出てくる可能性があります。その結果、自社とマッチしない人材を採用し続けるという悪循環に陥ることも起こりかねません。そのような事態を避けるために、採用基準が必要なのです。
採用のミスマッチが起きる原因や、予防方法については以下の記事で詳しく解説しています。ミスマッチが多く、人材が定着しないことに悩んでいる採用担当の方はぜひ参考にしてください。
ミスマッチとは?採用活動でミスマッチが起きる原因や対策を解説
合否の判断を速やかにおこなえる
企業として統一された採用基準がないと、面接官の主観で判断がばらつくことも多々あります。場合によっては、面接官の意見が正反対に分かれ、合否判断が難しくなることもあるでしょう。統一基準があることで、面接官による判断のバラつきを防ぎ、合否判断を迅速におこなうことが可能になります。
採用基準がない/適切でない場合に起こる問題点
採用基準がない、あるいは適切でない場合、採用実務に大きな影響を与えます。ここでは、この場合における問題点を解説します。
ミスマッチによる早期離職リスク
採用基準がない、または適切でない場合、社風や価値観、志向性の不一致によって採用ミスマッチを起こす恐れがあります。
こうした採用ミスマッチによって、入社後にパフォーマンスが発揮できない、モチベーションが保てないなどから早期離職を引き起こすリスクもあるでしょう。
こうした採用ミスマッチを起こさないように、価値観や志向性、行動特性などの評価基準を設定することが重要です。
採用効率の悪化
求める人材が共通認識されていないと、人事や現場、役員などの間で意見が分かれ、人材採用の合否決定が難航する恐れがあります。この調整に時間を要した結果、求職者が選考過程で離脱してしまうといった事態も起こり得ます。
その他、能力要件など形式的な基準を明確化しないことで、面接に通すべきでない求職者を選考してしまうリスクもあります。採用活動全体をスムーズに進めるためには、評価基準の明確化は必要不可欠であるといえるでしょう。
活躍人材を採用するために重視すべき、3つのポイント
自社で活躍する人材を採用するには、次の3つを重視すべきです。
- 社風・カルチャー
- 高業績を上げる人材の行動特性(コンピテンシー)
- 人材要件
順を追って説明します。
社風・カルチャー
まず1つ目は、社風・カルチャーです。求職者の価値観が自社の社風・カルチャーに合っていなければ、採用ミスマッチを引き起こす可能性が高まります。
序列を重んじる企業とフラット志向な人材の合致は難しく、挑戦的な風土の企業では、保守的な人材はミスマッチとなるでしょう。このような採用ミスマッチを防ぐため、自社の社風やカルチャーに合う価値観を持つ人材の採用基準を作る必要があります。
高業績を上げる人材の行動特性(コンピテンシー)
2つ目は、活躍人材を採用する効果的な手段といえるコンピテンシーがあげられます。コンピテンシーは、自社で高業績をあげる社員の価値観や行動特性を指標とする手法です。このコンピテンシーを採用基準に取り入れることで、自社で活躍する人材を採用できる可能性が高まります。
行動パターンや考え方など、自社のコンピテンシーに合った人材の基準を盛り込み、活躍人材を採用しましょう。コンピテンシーの基本的な内容や、コンピテンシーを活用した面接方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
優秀な人材とは?特徴や見分け方、採用・定着のコツを簡単解説
優秀な人材を採用して、自社の事業をさらに発展させるためにも、ぜひ参考にしてください。
人材要件
3つ目は、求める能力やスキルなどの人材要件を定めることです。この要件を明確化することで、自社の求める水準の求職者を集めることが可能になります。
ただし、人材要件のハードルが高すぎると、応募者数を見込めなくなるため、必須のスキルや能力に限定することがポイントになります。「必須」と「尚可」に分けて要件を記載することも効果的です。
人材要件の項目や定め方については、当サイトの別の記事で詳しく解説しています。人材要件が定まっていない場合や、定め方がわからないという方はぜひ参考にしてください。
人材要件の定義や作り方、条件の優先順位付け・ペルソナ設定のコツ
求める人材を採用するための採用基準の決め方
以下6つのステップで進めるとスムーズに策定できます。
- 就活・転職市場のトレンドを把握
- 業務に必要なスキルをヒアリング
- コンピテンシーモデルを設定
- 基準を書き出し、優先順位を決める
- 人材要件との整合性をチェック
- 各選考フローに反映
ステップごとに考慮するポイントを解説します。
【1】就活・転職市場のトレンドを把握
採用基準が世間の流れと逆行していたり、採用ターゲット層の価値観と乖離していたりすると、採用活動が難航する懸念があるため、トレンドの把握が必要です。たとえば、ワークライフバランスを重視する人が多い20代を採用するのに、「プライベートより仕事優先」「ノルマ重視」という志向を基準にするのは賢明とはいえません。
業界や職種によっても有効求人倍率には大きな差があり、現状を踏まえた基準の設定も大切です。人手不足の業界・職種にもかかわらず基準が古いまま(=人手が足りていたときは通用していた基準)だと、欠員の補充もままならないなど、事業に悪影響が出る可能性があります。
【2】業務に必要なスキルをヒアリング
現場社員や採用する部署の管理職にヒアリングし、業務上不可欠なスキルや資格を明確にすることが重要です。スキルや資格の条件を満たしていないにもかかわらず合格と判断してしまうと、入社後にミスマッチによって早期離職する可能性があります。
応募者、採用担当者をはじめとする関係者の時間を浪費しないためにも、必須条件の確認・周知は非常に重要です。
【3】コンピテンシーモデルを設定
優秀な社員の行動特性をもとに「コンピテンシーモデル」を以下の流れで作成します。
- 高いパフォーマンスを発揮している社員を選定する。
- 集約・整理されたコンピテンシーから必要な項目を決定する。
- ヒアリングをおこない、業績に関連する行動と、その行動に至った考え方を把握する。
- 高いパフォーマンスを発揮できる考え方と行動をコンピテンシーモデルに設定する。
ヒアリングをおこない、成果に結びつく行動と、その行動に至った考え方の洗い出しが必要です。理想的な社員がいない場合は、求める人物像をベースに項目を作ります。コンピテンシーについてさらに詳しく知りたい方は「コンピテンシーの意味とは?面接への活用法、モデル作成のメソッドも解説」をご覧ください。
【4】基準を書き出し、優先順位を決める
ここまであげた項目を全てまとめ、必須条件、十分条件の分類や、優先順位を決めてください。条件をある程度絞ることで、基準が過度に厳しくなることを回避し、評価が僅差の応募者から合格者を選ばなければならないときの判断材料にもできます。
【5】人材要件との整合性をチェック
実際に運用する前に、あらためて人材要件とのズレがないか確認します。人材要件は採用の根拠となる人物像であり、採用基準はそれを「ふるい」として機能するよう落とし込んだものです。合否判断の整合性が揺らがないよう、方向性が矛盾していないかチェックが必要です。
【6】各選考フローに反映
書類選考、筆記試験、一次から最終面接まで、各段階でどのような基準を適用するかを決定します。コミュニケーション力に関する項目を面接時の基準にするなど、試験の方法別に分類するほか、選考が進むにつれてハイレベルな基準になるよう、段階を設定するのも効果的です。
選考フローについては以下の記事で詳しく解説しています。選考フローの作り方や、パターンについて図を使ってわかりやすく解説しているので、選考フローの構築や見直しを検討している方はぜひ参考にしてください。
採用フロー作成で採用課題が見えてくる?|チャート図付き【新卒】
参考にしたい採用基準の設定例
ここまでのポイントを踏まえ、活用しやすい採用基準の例を紹介します。
<適切な例/経理職の場合>
【書類選考】
必須条件:大学卒以上、会計・経理の実務経験1年以上、日商簿記3級、普通自動車運転免許
歓迎条件:管理会計・決算・監査の実務経験、経理の実務経験3年以上、日商簿記2級以上、税理士資格【筆記試験】
・合計◯点以上、かつ分野1で◯点以上、分野2で◯点以上で合格
・合計点が基準に達していても、どちらかの分野の基準を下回った場合は不合格【面接】
・志望動機を明確に説明できるか
・話す内容が矛盾したり、二転三転したりしないか
・業務の工夫や改善について、自分自身の経験に基づき動機、行動、結果を含めて説明できるか【最終面接】
・志望動機を明確に説明し、深掘りの質問に対して論理的に回答できるか
・当社でのキャリア形成について見通しを持って説明したり、希望を伝えたりできるか
・当社の事業領域に関する知識を問う質問に回答できるか「条件」は応募者の能力・適性に関する項目に絞り、選考の基準はなるべく「可・不可」を判断しやすい視点でまとめるか、コンピテンシーモデルと対比できるような設問にしておくと便利です。
採用基準を決めるときの注意点
採用基準を決めるときの注意点は、「新卒と中途で基準を分ける」「適性・能力に関係のない項目を設定しない」ことです。これらに注意しないと起こりうるデメリットと、基準を策定するときのポイントを解説します。
新卒と中途で基準を変える
新卒採用では将来性のある人材を、中途採用では即戦力人材を採用するのが一般的であるため、基準を変えなければ思うような人材を確保できません。ここでは、新卒採用と中途採用の基準を作るうえでのポイントを紹介します。
新卒採用は応募者の人柄を重視する
新卒採用の場合、実務経験がないため、応募者の性格や考え方などの人柄を重視する採用基準を作ります。応募者の人柄と自社の社風がマッチするかを見極めることで、ミスマッチによる早期離職を防止できます。
応募者の人柄を見抜くポイントは、チャレンジ精神や協調性、誠実性があるかを確認することです。優秀な社員の行動特性をもとに作ったコンピテンシーモデルがあると、採用基準が作りやすくなります。
中途採用は応募者のスキルや経験を重視する
中途採用の場合は、即戦力となることを期待しているケースが多いため、人柄に加えてスキルや経験を重視して採用基準を作ります。エンジニアであれば「アジャイル開発手法を用いての開発経験のある人材」、営業職であれば「海外企業への営業経験がある人材」というように、自社の求める人材の条件をできるだけ具体的に設定してください。
ただし、近年は中途採用でも、人材の将来性を見込んで採用するポテンシャル採用に取り組む企業が出てきており、スキルや経験を重視しないケースもあります。ポテンシャル採用の場合は、新卒採用の基準に加え、社会人基礎力が身に付いているかを基準とするのが一般的です。ポテンシャル採用について詳しく知りたい方は「ポテンシャル採用とは?メリット・デメリット、大手企業での事例を紹介」をご覧ください。
適性・能力に関係ない項目を設定しない
採用基準はできる限り具体的であることが望ましいものの、適正や能力に関係のない要素を含めると就職差別につながる可能性があります。就職差別につながる可能性があるのは、「本人に責任のない事項」と「本来自由であるべき事項」の大きく2つです。細かな項目は以下になります。
| 本人に責任のない事項 | ●本籍・出生地に関すること ●家族に関すること ●住宅状況に関すること ●生活・家庭環境に関すること |
|---|---|
| 本来自由であるべき事項 | ●宗教に関すること ●支持政党に関すること ●人生観・生活信条に関すること ●尊敬する人物に関すること ●思想に関すること ●労働組合・学生運動などの社会運動に関すること ●購読新聞・雑誌・愛読書に関すること |
選考基準の話からは逸れますが、これらに加えて、身元調査や合理的・客観的に必要性が認められない選考段階での健康診断の実施にも注意が必要です。どちらも本人に責任のない情報が入る可能性があり、結果として就職差別になりかねません。
採用基準の見直しが必要なケースとは
すでに採用基準を策定・運用している場合でも、次の状況が見られたら改善の検討が必要かもしれません。
書類選考の通過者が少ない
十分な応募数があるにも関わらず、書類選考で多くの応募者を落としている場合、書類選考の採用基準が厳しすぎるか、項目が多すぎる可能性があります。書類選考の採用基準を「絶対に外せない条件(MUST条件)」と「あれば望ましい条件(WANT条件)」に区分するよう見直すことで、適切な書類選考が可能になります。
応募数が極端に少ない
そもそも応募数が極端に少ない場合は、採用基準が非現実的になっていることや、基準に対して給与が低い可能性があります。期待するスキル・経験など条件が数多くあげられていると、応募を敬遠されてしまう場合もあります。まずは募集要項、採用基準ともに「必須条件と歓迎条件に分ける」ことから始めてください。
現場と人事の合否の感覚が一致していない
現場社員と採用担当者の考え方や感じ方が異なるのは往々にしてあることですが、採用基準を設定しているはずなのに合否の不一致が多いようであれば、基準自体に問題があるかもしれません。「コミュニケーション能力が高い」などの抽象的な基準は避け、「ロジカルに話すことができる」「相手の話を深く理解できている」「相手の考えを察することができる」といった具体的な基準が必要でしょう。具体的にどのような基準が必要か、現場と意見交換をしつつ再検討が必要です。
このような問題は面接評価シートの活用により解決できるかもしれません。面接評価シートは評価項目や基準を言語化したものです。共通の評価シートがあることで、現場と人事の考えに乖離が生まれることを防止し、面接の評価を平準化できます。
面接評価シートの作り方やサンプルは以下の記事を参考にしてください。
面接評価シートの作り方とは?作成のメリットや含める項目を紹介
【各段階別】採用基準を用いた人材の見極め方
ここでは、採用基準を用いた選考の各段階別における人材の見極め方を解説します。
書類選考
書類選考の段階では、経験やスキルなど、定量的な項目を採用基準としてスクリーニングします。
マッチする人材が極端に少なくならないよう、「絶対に外せない条件(MUST条件)」と「あれば望ましい条件(WANT条件)」に区分し、相対的に評価することで、効率的にスクリーニングが可能です。具体的には、MUST条件を満たした求職者のみ抽出し、そのなかでWANT条件を満たす項目が多い順から求職者を順位付けします。
適性検査
適性検査の段階では、求職者の能力や性格を定量的に診断した適性検査結果をもとに、採用基準と照らし合わせてスクリーニングします。
見るべきポイントとして、能力適性は、最低限必要な職業能力を要しているかの判断に活用することが一般的です。性格適性は、求職者の行動特性や価値観が自社にマッチしているかを判断することに有効でしょう。
また、新卒採用と中途採用では、適性検査の見るべきポイントが異なります。新卒採用では主に求職者のポテンシャル、中途採用では会社や配属部門とのカルチャーフィットを主に判断します。
適性検査を詳しく知りたい方は、「適性検査とは?目的や選び方、不正対策を徹底解説【23種類一覧表付】」の記事をご参考ください。
面接
面接段階では、書類選考や適性検査のような定量的に図れない、「印象」「人柄」「入社意欲」「価値観」など定性的な項目で判断します。
面接官の評価がばらつかないよう、決定した採用基準を面接評価シートに落とし込むことが重要です。たとえば、各評価項目毎に5段階評価で評定を設定するほか、面接官の所感などを自由記入できる項目を設け、面接評価シートを運用しましょう。
面接評価シートの作り方を詳しく知りたい方は、「面接評価シートの作り方とは?作成のメリットや含める項目を紹介」の記事をご参考ください。
あわせて設定したい不採用基準
能力不足や問題行動によって企業に悪影響をもたらす問題社員。この問題社員の存在は、他の社員にもマイナスに作用し、企業に重大なダメージを及ぼす恐れがあります。
ここでは、問題社員を採用するリスクを下げるための「不採用基準」について解説します。
不採用基準を設定するメリット
問題社員は、いくら指導しても業務遂行をまともにできない能力不足のほか、業務命令に従わない、仕事を怠ける、素行が悪いなどの「問題行動」によって、企業に悪影響をもたらします。不採用基準を設けることで、問題社員の採用リスクを下げられるほか、次のようなメリットが挙げられます。
- 企業に重大な悪影響が生じるリスクを下げられる
- 企業の秩序を保ちやすい
- 問題社員の対応労力を軽減できる
不採用基準の設定例
【書類選考】
・履歴書の学歴が卒業証明書と一致していない
・職務経歴書の経歴と雇用保険被保険者証や年金手帳などの内容と一致していない
【適性検査】
・虚偽性が〇以上
・ストレス耐性が〇以下
・協調性が〇以下
・職務適性の〇〇の項目が〇以下
【面接】
・履歴書の内容と面接の話に矛盾がある
・説明に一貫性がない
・退職した理由と志望理由の整合性がとれていない
・職務経歴書の経験を深掘りすると、整合性がとれない
知っておきたい問題社員の見抜き方
問題社員は、経歴詐称や早期離職の繰り返しをおこなうことが多くあります。また、提出すると不都合な書類を出し渋ることもあるでしょう。
こうした問題社員を見抜くため、採用基準を設定する以外でも、おこなうべきことがあります。
- 退職証明書の提出要請
- 年金手帳の加入歴や源泉徴収票の確認
- リファレンスチェックの実施
これらをおこなうことで、経歴詐称を見抜くことが可能になります。なお、リファレンスチェックとは、転職候補者の経歴や勤務状況、人物像について、前職の上司などの第三者を対象におこなう採用調査です。日本では、グローバル企業や外資系企業で一般的におこなわれています。
経歴詐称の見抜き方やリファレンスチェックの方法を詳しく知りたい方は、「経歴詐称を見抜く方法は?見抜くポイントや対処法を紹介」の記事をご参考ください。
人事が読むべき採用基準に関するおすすめ書籍2冊
採用基準をどうすべきか、悩んでいる人事担当者も多いでしょう。ここでは、概念から深く知り、基準策定に取り組む人事担当者におすすめ書籍を2冊紹介します。
採用基準 地頭より論理的思考力より大切なもの(伊賀 泰代著)
1冊目は、就職超難関企業のマッキンゼーで、採用マネジャーを12年務めた著者による採用基準の書籍です。コンサル業界で重視されている地頭の良さだけではないとし、リーダーシップの重要性をさまざまな角度で解説しています。重視すべきリーダーシップをわかりやすく説明している、人事必読の1冊です。
(※参考)Amazon:「採用基準 地頭より論理的思考力より大切なもの | 伊賀泰代 」
新卒採用基準(廣瀬 泰幸著)
2冊目は、株式会社リクルートで幅広く人材育成を支援した傍ら、講師や就活コーチングをおこなうなど、人材ビジネスに精通した著者による新卒採用基準の書籍です。あらゆる企業が注目する視点を、新卒採用の5つの基準としてわかりやすくまとめています。また、新卒採用にスポットを当て、ポテンシャルを見る要素を項目化しているため、新卒採用時に最適な1冊です。
(※参考)Amazon:「新卒採用基準: 面接官はここを見ている | 廣瀬 泰幸 」
まとめ
採用基準は、書類選考から最終面接まで全ての選考過程において不可欠です。普段は見過ごしがちな細かい点ですが、「できるだけ曖昧な表現を排除する」ことで、誤解を生みにくく明確な基準に近づきます。スムーズな採用選考の実施を目指し、意識してみてください。
ただし、肝心の「求める人材からの応募」がなければ苦労して策定した労力が水の泡です。採用基準を具体的に落とし込む過程では、実際の求人内容が求職者に「いかに伝わりやすく、いかに響くか」を意識することも重要です。応募してくる人材の質にお悩みの採用担当者の方は「『欲しい人材からの応募がこない』を解決する方法。」をぜひご覧ください。
無料ダウンロード
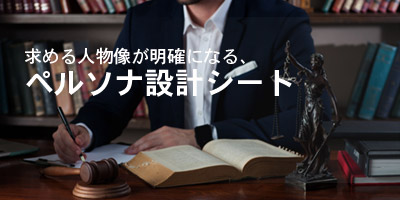
無料ダウンロード
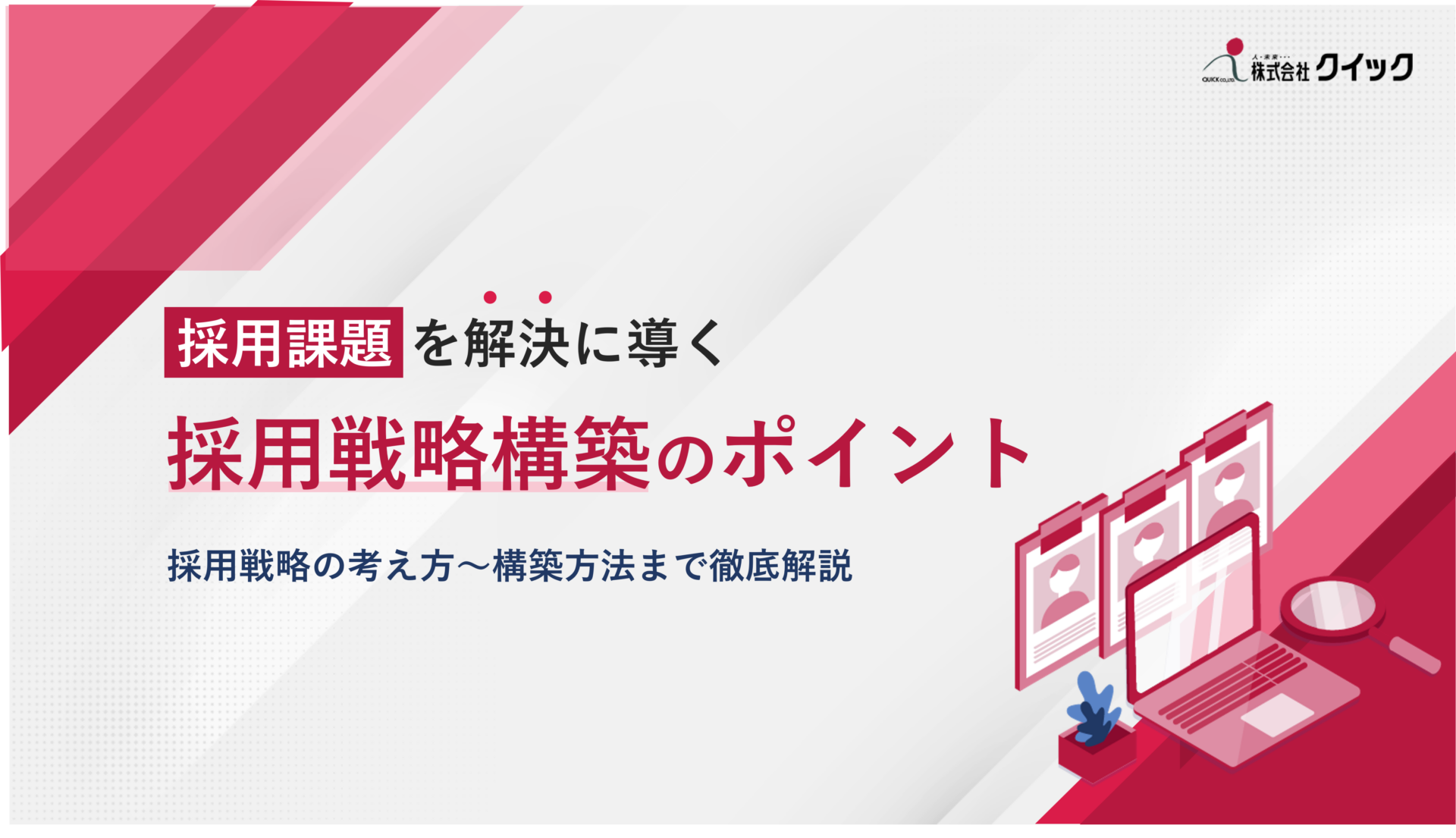
採用課題を解決に導く採用戦略構築のポイント
採用活動においても、パフォーマンスの要となるのは「戦略」の設計です。 コンサルティングサービス「採活力」は、貴社に最適な採用コミュニケーションを設計し、採用活動を成功へと導きます。
セミナー情報