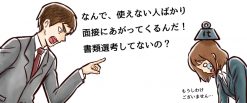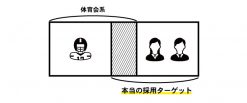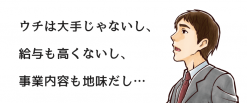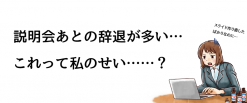人材要件とは
あらためて、人材要件の定義や似たような言葉である「採用ペルソナ」との違いをまとめます。
人材要件の定義
人材要件とは、企業の理念や今後の事業展開を踏まえて、「どのような人材が必要か」を明確化したものです。
一般的に「求める人材像」などと表現され、所有しているスキルや資格をはじめ、経験・属性・人柄などを多角的に定義していきます。
採用活動において、優秀な人材の獲得は会社の成長に欠かせませんが、人材要件がないと「優秀な人材」のとらえ方が担当者によって変わってしまうリスクがあります。
会社として共通認識を持ったうえで採用活動を実施するためにも、人材要件の定義は必要不可欠でしょう。
採用ペルソナとの違い
人材要件と似たものとして「採用ペルソナ」が挙げられます。人材要件は、自社が求めるスキルや経験などを明確にした人材像を指し、具体的な基準を示します。例えば、「〇〇技術の知識が必要」というような条件です。
一方、「ペルソナ」は人材要件を基に、人物像をより具体化したものです。ペルソナは、スキルや経験だけでなく、候補者の性格、価値観、生活背景なども含めた詳細なプロフィールを描きます。例えば、「技術があり、チームとの協力が得意な32歳の佐藤さん」といった具体的な候補者像です。
つまり、人材要件で設定したスキルや経験を基に、架空の人物プロフィールを描いたものがペルソナです。ペルソナでは、家族構成、出身大学、所属部活などの情報のほか、週末の過ごし方なども具体的に設定します。これにより、採用したい人物像のリアリティを高めることができます。
人材要件を設定する目的
人材要件を設定することは、企業が求める人材像を明確にし、採用活動を成功に導くために重要です。
人材要件がなくても採用活動自体は可能ですが、本質的な成功を目指すならば、人材要件は不可欠といえるでしょう。
ここでは、改めて人材要件を設定する様々な目的について解説します。
経営戦略と採用戦略の一貫性が保てる
人材要件を設定することで、経営戦略と採用戦略の一貫性を確保できます。経営戦略と採用戦略の整合性を持たせることで、企業の目標達成により近づくことができます。
人材要件が明確であれば、採用担当者は適切な候補者を見極めやすくなり、内定を出す際の基準も共通認識を持って運用できます。また、採用活動の過程で経営方針や企業理念を候補者に伝えることができ、求職者の理解と共感を得ることにもつながります。これにより、採用後の高いパフォーマンスを引き出しやすくなり、企業全体の成長に貢献する人材を獲得できる可能性が高まるでしょう。
採用基準の統一
人材要件を設定する目的の一つに「採用基準の統一」があります。
採用基準を統一することで、以下のメリットが得られます。まず、企業全体で一貫した評価基準を持つことで、面接担当者間の評価のばらつきを抑えられます。これにより、どの担当者が面接を行っても、応募者を客観的かつ公平に評価できるようになります。また、採用要件が明確になることで、採用活動の振り返りや分析がしやすくなり、今後の採用戦略の改善にもつながります。
時間とコストの削減
明確な人材要件があれば、適切な候補者を迅速に見つけ出し、面接や選考のプロセスをスムーズに進めることができるため、採用活動にかかる時間とコストを抑えることができます。
例えば、求める具体的なスキルや経験を事前に定義しておくことで、書類選考や面接段階での無駄なやりとりを減らすことができます。また、採用のミスマッチが減少するため、再採用にかかるコストも抑えられます。
人材要件を明確にすることで、採用活動の効率化とコスト削減を実現し、企業にとって最適な人材確保につなげていきましょう。
採用ミスマッチや早期退職の防止
人材要件があることで、採用ミスマッチや入社直後の離職防止につなげられます。
人材要件がない場合、時間をかけて採用した人材が早期退職に至るケースがあります。会社が求める条件と人材が持っているスキルや経験、考え方の不一致が原因です。
人材要件が明確であれば、条件を絞ったうえで自社に適した人材を採用できるため、採用ミスマッチのリスクを減らすことができます。採用ミスマッチの防止により、早期退職など、人材流出の抑制にもつながるでしょう。
人材要件で定義する項目
人材要件を構成する際には、具体的な項目を定義することが重要です。これにより、企業が求める人物像を明確にし、採用活動の効果を最大化することができます。例えば、属性やスキル・経験・知識、性格・志向性などの具体的な要件を設定することで、候補者を選定する基準が明確になります。
属性
人材要件を定義する際には、候補者の属性も重要な要素です。属性には、年齢や性別、居住地域などが含まれます。これらの条件を設定することで、求める人材の背景やライフスタイルに合った候補者を選定しやすくなります。ただし、属性に関する条件は法律や社会的配慮を踏まえて設定し、差別や偏見を避けるよう注意が必要です。
スキル・経験・知識
スキルや経験、知識は、求める役職での業務遂行に必要不可欠な要素です。スキルには専門的な技術や資格、業務遂行に必要な能力が含まれます。経験は、過去の職務で得た実績や具体的な業務内容を指し、知識は業界や職種に関連する専門知識を含みます。これらを明確にすることで、応募者が業務に即戦力として貢献できるかどうかを判断する基準が整います。
性格・志向性
性格や志向性は、候補者の働き方や職場での適応力に大きく影響します。性格には、協調性や主体性、ストレス耐性などが含まれ、志向性には職業に対する価値観や目標が含まれます。企業の文化やチームのダイナミクスと一致するかどうかを評価するために、性格や志向性を具体的に定義することが求められます。これにより、長期的な適応と成長が期待できる人材を見極めることができます。
このような項目を定めておくことで、求職者の選定がスムーズになり、採用活動の効率化にもつながります。
採用関係者間での共通認識も生まれやすいため、まずは上記の項目を定義してみてください。
人材要件の作り方
人材要件に盛り込むべき要素は多岐にわたります。
要件を固めていくにはスケールの大きな段階から細かい段階へと落とし込み、具体化するよう意識しましょう。なお検討初期に、幅広いアイデアを出す作業方法としては「ブレインストーミング」などの手法があります。
企業理念・経営戦略を確認する
まずは、企業理念や経営戦略を確認して、自社の方向性と採用計画が連携し、矛盾や非現実的な設定が生じていないか精査しましょう。
採用の背景と目的の明確化も重要です。
たとえば、新規事業開発や社員の退職によるリソース減少などが背景にある場合、長期的な増員や短期的な人員の補充などが目的になります。
業務内容を整理する
実際の募集案件に関する業務内容を整理しましょう。
企業理念・経営戦略を確認した上で業務内容をすることで、人材要件定義に必要な情報が整います。
必要に応じて関係部署へヒアリングすることもおすすめです。これにより、業務内容やそれに必要な要素について詳細にリストアップすることが可能となります。
人材要件定義に必要な設定項目を埋める
上記2つの対応を経たうえで、人材要件定義に必要な項目を埋めましょう。
実際の要件定義に活用できるフレームワークについては、後述しております。
訴求点を明確化する
人材の必要十分条件、人柄や行動特性をまとめることで、採用ターゲットに届きやすい訴求ポイントをより明確にできます。
ターゲットなら自社のどのような点に魅力を感じそうか、人材要件に照らし合わせて取捨選択しましょう。
自社の強み・弱みをまとめ、相手の人柄によってはあえて弱みを見せることが「この会社はよい面だけでなく、課題も含めて伝えてくれる」と好印象にとらえてくれる可能性もあります。
人材要件を定義するフレームワーク
人材要件を定義するために活用できるフレームワークをご紹介します。
ペルソナ設計
前述したように、ペルソナとは仮定の人物像(の設定)で、主にマーケティングで使われる手法を採用に応用したものです。
ここまで整理した条件を足がかりに、性格や興味関心、家族構成、学校や前職での経験、仕事や生活に対する価値観、趣味や休日の過ごし方など「キャラクター」を作り上げるように設定します。
実際に活躍できる人物像とずれないよう、現場の社員に作成やチェックの協力をしてもらいましょう。
パターン数や更新の頻度は必要に応じて決定してください。
ペルソナが設計できたら、面接の質問を考えたり、選考で通過者を絞り込んだりするときに活用しましょう。
人材要件フレーム
人材要件フレームは、採用活動において求める人材像を明確化するための効果的なフレームワークです。このフレームでは、人材に求める条件を「MUST(必要条件)」と「WANT(十分条件)」の2つに分類して設定します。
MUSTは、業務遂行に最低限必要なスキルや経験、必須の資格、そして職場に適応するために欠かせない価値観や性格特性などを含みます。一方、WANTは、保有していれば望ましいが必須ではないスキルや経験を指します。
このフレームを活用することで、採用要件に自然と優先順位をつけることができ、採用担当者間で求める人材像の認識を統一しやすくなります。
さらに、「BETTER」や「NEGATIVE」の要素を加えることで、より詳細な人材要件を定義することも可能です。
BETTERは企業にとって大きな利点となるスキルや経験、NEGATIVEは避けたい特性や経験を示します。これにより、求職者の評価がより客観的かつ効率的に行えるようになり、採用のミスマッチを防ぐことができます。
人材要件フレームを活用することで、経営戦略に沿った採用戦略の立案や、効果的な採用活動の実現につながります。また、このフレームワークは新卒採用と中途採用で条件を変えて設定することも可能であり、柔軟な運用が可能です。
コンピテンシーモデル
コンピテンシーとは、「優秀な人材が持つ考え方や行動の特性」のことです。
企業においては、高いパフォーマンスを発揮している社員の行動・考え方=仕事の進め方がコンピテンシーとなります。
ヒアリングやアンケートなどを通じて行動特性を集約・整理し、採用する職種に合わせてモデル化したのが「コンピテンシーモデル」です。
コンピテンシーモデルを作るには、対象の社員本人や上司、同僚にヒアリングやアンケートをおこない「ある状況でどのような考えに基づきどのような行動をとるか」を探ります。採用においては、「このような状況のとき、あなたはどのような行動をとりますか」などと質問し、コンピテンシーモデルに近いかどうかで適性を判断できるでしょう。
<行動特性の例>
Q.営業先で提案した商品の導入を断られた場合、どのようにフォローするか?
A.そのまま押し続けても印象が悪化するだけと考え、同じ商品で食い下がることは控える。
「それではこのような困りごとではお役に立てるのではないかと思います」と別の商品を案内し、その場で契約に至らずとも「いざというときに相談できる」相手として覚えてもらえるように話題を切り替え、後日の訪問につなげる。
そのためにも、業界研究や商材理解は怠らないようにしている。
氷山モデル
氷山モデルは、人材要件を定義する際に非常に有効なフレームワークです。このモデルでは、人材の表面的な特徴だけでなく、内面的な要素も含めて全体像を捉えることができます。
具体的には、氷山の水面上に相当する「行動」と、水面下に位置する「知識・スキル」「マインド」の3つの要素から人材要件を定義します。
「行動」は最も可視化しやすく、業務遂行に直結する重要な要素です。一方、「知識・スキル」と「マインド」は、その行動を支える土台となる要素で、直接目に見えにくいものの、人材の本質を形成する重要な部分です。
このアプローチを採用活動に活用することで、表面的な評価だけでなく、候補者の潜在的な能力や適性も含めた総合的な判断が可能になります。
氷山モデルを用いて人材要件を設定する際は、まず自社に必要な「行動」を明確にし、次にそれを支える「知識・スキル」「マインド」を具体化していきます。このプロセスを通じて、より精度の高い採用基準を策定し、効果的な人材獲得につなげることができます。
STP法
STP法は、人材要件を定義する際に効果的なフレームワークの一つです。特に新卒採用において有用性が高く、採用戦略の最適化に役立ちます。
このアプローチでは、まず「Segmentation(市場細分化)」として、求職者市場を学部・学科、志望業界、所属ゼミやサークルなどの基準で細分化します。次に「Targeting(ターゲット選定)」で、自社にとって最適な採用ターゲットを特定します。最後に「Positioning(ポジショニング)」で、他社との差別化ポイントを明確にし、独自の採用戦略を構築します。
STP法を活用することで、採用活動の焦点を絞り、効率的な人材獲得が可能になります。例えば、特定の学部や志望業界にターゲットを絞ることで、自社の求める人材像により近い候補者にアプローチできます。また、自社の強みを活かしたポジショニングにより、競合他社との差別化を図り、優秀な人材の獲得確率を高めることができます。
GRPIモデル
GRPIモデルは、Goal(目標)、Role(役割)、Process(手順)、Interaction(関係性)の4つの要素から構成され、包括的な人材像を描くのに役立ちます。
採用活動においてGRPIモデルを活用する際は、以下のように各要素を解釈し、具体化していきます:
Goal
企業や組織の目標を明確にし、求める人材がどのような成果を上げるべきかを定義します。
Role
目標達成に必要な役割を特定し、候補者に期待される職務や責任を明確にします。
Process
役割を遂行するために必要なスキルや知識、経験を具体化します。これには業務手順の理解も含まれます。
Interaction
チームや組織内での良好な関係性構築に必要なコミュニケーション能力や価値観、マインドセットを定義します。
このフレームワークを用いることで、経営戦略と連動した採用要件を設定でき、採用ミスマッチの防止にも効果的です。また、応募者にとっても期待される役割や必要なスキルが明確になり、自己評価がしやすくなります。
GRPIモデルは、新卒・中途採用問わず活用でき、採用後の人材育成計画にも応用可能な汎用性の高いツールです。採用担当者は、このモデルを活用して効果的な採用活動を展開し、自社に最適な人材の獲得を目指すことができます。
人材要件を作成するときのポイント
続いて、新卒採用、中途採用の人材それぞれで、人材要件を作成するときに気をつけるべきポイントを紹介します。
新卒採用・中途採用で条件を変える
採用要件を定義する際には、新卒採用と中途採用で条件を変えることが重要です。これは、求職者の経験やスキルセットが異なるためです。
新卒採用では、選考対象が学生であるため、社会人経験がないことが前提となります。このため、スキルよりも「性格」「価値観」「仕事への熱意」「ポテンシャル」などを重視します。新卒採用では、将来的な成長や企業文化への適応力が重要視されます。
一方、中途採用では、既に社会人経験がある求職者が対象です。そのため、「スキル」「能力」「知識」「業務経験」「前職での実績」などが評価の中心となります。中途採用では、即戦力としての能力や、具体的な業務遂行能力が求められます。
このように、新卒採用と中途採用では、求める要件や評価基準が異なるため、それぞれに適した採用要件を設定することが、効果的な採用活動を実現するためのポイントです。これにより、採用ミスマッチを防ぎ、企業にとって最適な人材を確保することが可能となります。
求める条件を厳しくしすぎない
採用要件を設定する際に、条件を厳しくしすぎると、該当する人材が極端に少なくなり、採用活動が難航する可能性があります。特にMUST(必須条件)を増やしすぎると、本来なら採用に値する人材を逃してしまう恐れがあります。
企業としては、優秀な人材を獲得したいというのが本音ですが、採用要件に優先順位をつけずに多くの条件を設定すると、実際には自社の業務に適応できないケースもあります。優れたスキルを持つ人材が必ずしも自社に適しているとは限らず、入社後のミスマッチを引き起こす可能性もあります。
そのため、求める条件に優先順位をつけ、必要最低限の要件を明確にすることが重要です。特に、入社後に育成可能なスキルや経験は、あまり厳しく求めない方が良いでしょう。これにより、より広い範囲の候補者から応募を受け入れ、自社に適した人材を見つけるチャンスを広げることができます。
このように、求める条件を厳しくしすぎず、優先順位を明確にすることで、採用ミスマッチを防ぎ、効果的な採用活動を実現することができます。
応募者が得られるメリットも整理しておく
採用活動では、自社が求める条件を明確にするだけでなく、応募者にとってのメリットを整理することも重要です。応募者は、自社で働くことによってどのような利益を得られるのかを理解することで、応募の動機が高まります。従って、自社の魅力や提供できる価値を積極的にアピールすることが求められます。
例えば、自社が提供する研修制度やキャリアパス、働きやすい職場環境などの情報を具体的に伝えることで、応募者の関心を引くことができます。また、競合他社と比較した際の優位性を明示することで、応募者にとっての自社のメリットをより際立たせることができます。これにより、自社の魅力を効果的に伝え、応募者の質と数を向上させることが可能になります。
応募者が自社に入社することでどのような成長機会やキャリアの発展が期待できるのかを示すことも、成功する採用活動の鍵です。具体的なメリットを整理し、求職者に対して分かりやすく伝えることで、自社の魅力を高め、より優れた人材の獲得につなげましょう。
効果検証をおこないPDCAを回す
採用活動は、毎回効果と検証を実施することが大切です。振り返りの際には、人材要件についても効果検証をおこなってください。
設定した人材要件でどのくらいの応募があったのか、面接を実施できたのは何人かといった検証をおこないましょう。同時に、目標に達していない場合は改善を重ねていくことが重要です。
どんなに効率的な採用方法を用いたとしても、人対人の採用は一筋縄ではいきません。PDCAを回しながら、少しでも理想の採用活動を確立できるように努めましょう。
まとめ
人材要件作成の流れとポイントを紹介しました。一つひとつプロセスを踏んで人材要件を作成していくことが重要ですが、それだけではどうもうまくいかない…と感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ターゲット像を作る過程で発生する悩みを解決するためのヒントを、「欲しい人材からの応募がこない」を解決する方法。で紹介しています。こちらもあわせてご覧ください。
よくある質問
Q1.人材要件とは?
人材要件とは、企業の理念や今後の事業展開を踏まえて、「どのような人材が必要か」を明確化したものです。
一般的に「求める人材像」などと表現され、所有しているスキルや資格をはじめ、経験・属性・人柄などを多角的に定義していきます。
Q2.人材要件のフレームワークとは?
「企業理念・経営戦略を確認」→「条件をMUST/WANT/NEGATIVEに分類」→「望ましい性格・人柄を設定」→「訴求点を明確化する」の4つのステップを経ることが、人材要件を設定するフレームワークです。
無料ダウンロード
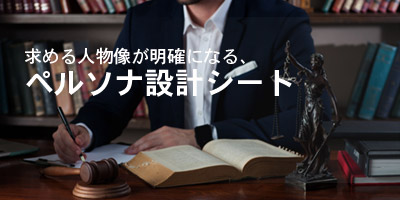
無料ダウンロード
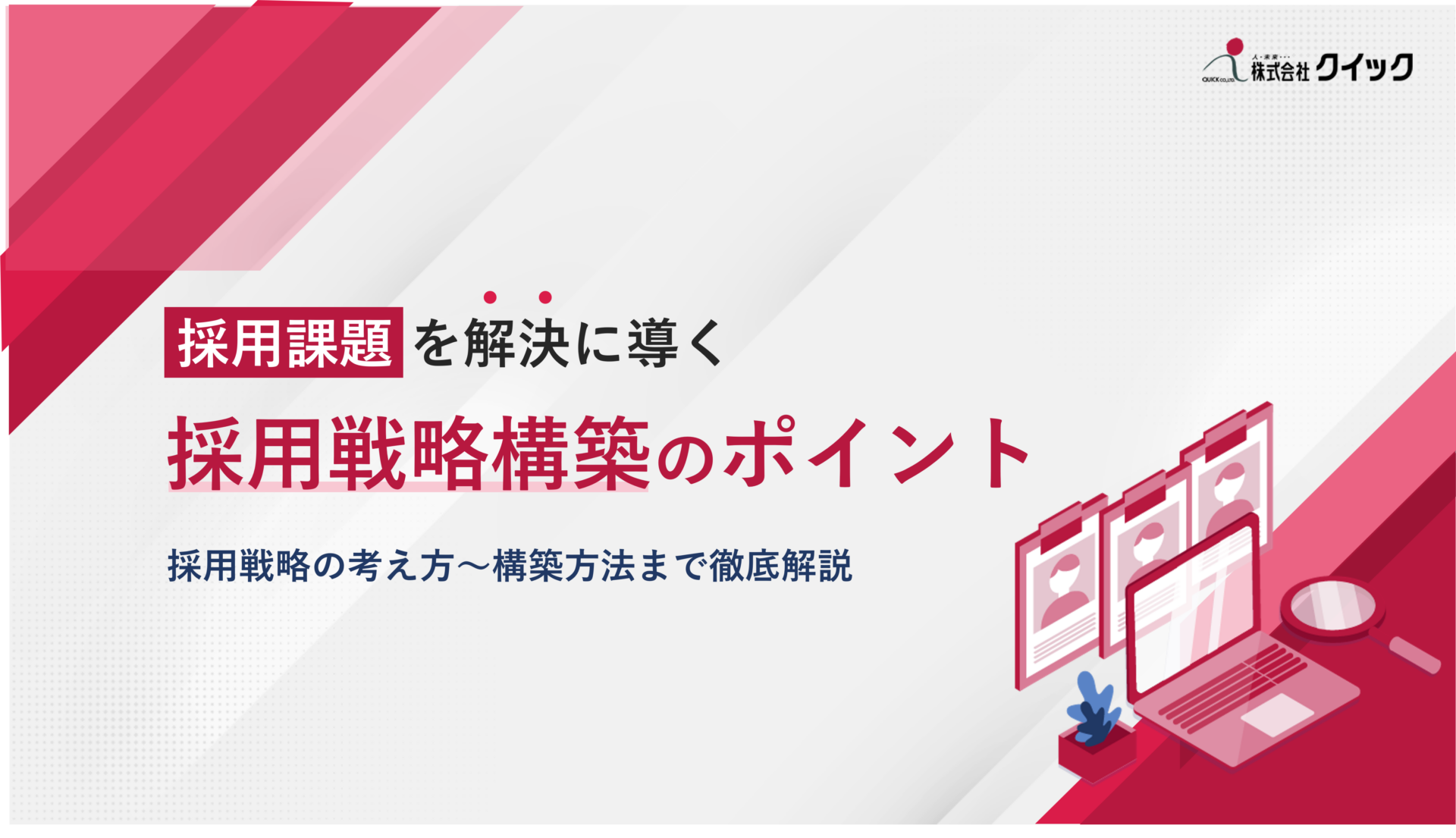
採用課題を解決に導く採用戦略構築のポイント
採用活動においても、パフォーマンスの要となるのは「戦略」の設計です。 コンサルティングサービス「採活力」は、貴社に最適な採用コミュニケーションを設計し、採用活動を成功へと導きます。
セミナー情報

あわせて読みたい