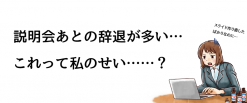採用活動では面接だけでなく面談も重要
近年の採用競争激化の影響で、企業が「選ぶ立場」から「選ばれる立場」への移行が進行しています。その結果、面接だけではなく面談も採用成功に重要な要素となってきています。
面談では、個別の対話で候補者の本質が見え、企業文化への適合度も把握できます。オファーを強化すべき候補者が明らかになることで、より効果的なアプローチをすることが可能となります。
面談とは何か
面談の定義と目的
採用活動における面談は、求職者の応募を促したり、内定者の入社意思を固めたりすることを目的とした話し合いの場です。選考の合否には直接関係なく、求職者と対等な立場で話すのが特徴です。優秀な人材との接点を作るために、面談を積極的に実施する企業もあります。ここでは、面談を実施する以下3つの目的について解説します。
・相互理解を深める
・求職者の自然な姿が見られる
・自社の魅力をアピールできる
相互理解を深める
面談には、求職者と企業側の相互理解を深める目的もあります。面接と違って面談では合否に関わらないため、求職者とフランクに会話しながら、相互に質問して疑問点を解消できます。求職者の入社後のイメージを膨らませられるためミスマッチ防止も期待できます。面談担当者は応募や内定受諾につながる情報発信を心がけてください。
求職者の自然な姿が見られる
求職者の自然な姿を見る目的で、フランクに話しやすい面談を実施します。面接では、求職者が話す内容を考えてきているケースがあり、普段の姿とギャップがある可能性があります。しかし面談では合否が関わらないと事前に伝えることで、求職者がリラックスして話せる雰囲気を作れます。求職者の自然な姿を見て、自社にマッチした志向性や価値観を持っているか見極めやすくなります。このようにフランクな会話をすることが求められる面談では、アイスブレイクがより一層重要となります。
また、求職者から引き出した悩みや疑問を他の求職者が抱いている場合もあります。引き出した情報を活用して、説明会で話す内容や自社の採用サイトに掲載する情報を求職者に寄り添ったものに変えることで、次年度以降の採用活動の改善につながります。
自社の魅力をアピールできる
面談の目的は、求職者に合った自社の魅力をアピールすることです。説明会や自社の採用ページで発信する魅力は大勢に向けた内容であり、求職者によっては魅力と感じない可能性があります。面談では、自社に求職者の経験やスキルが生かせる場があると具体的に説明したり、モデルとなる社員を交えて話したりできるため、自社により魅力を感じてもらいやすくなります。
面談の3つの種類
面談は、目的ごとにいくつかの種類があり、1対1だけでなく複数人で行われる場合もあります。ここでは以下3つの種類の面談について解説します。
【1】カジュアル面談
【2】リクルーター面談
【3】内定者面談
カジュアル面談
カジュアル面談は、応募促進や転職意思の固まっていない優秀な人材と接点を持つための取り組みとして、採用選考開始前に実施します。選考ではないため求職者の参加ハードルが低く、就職や転職意思が固まっていない潜在層にも参加してもらいやすいのがメリットです。
リクルーター面談
リクルーター面談は、新卒採用時に用いられる手法です。主にリクルーターの出身大学の後輩に接触し採用につなげるために行われます。自社を知らない学生に認知してもらう、自社を知っている学生にはより深く理解してもらうために、大学やカフェなどの社外でリラックスした雰囲気で行われるのが一般的です。リクルーター面談についてより詳しく知りたい方は「リクルーターとは?リクルーター面談の役割や実施時のポイントを解説」をご覧ください。
内定者面談
内定者面談は、内定者の入社意思を固めたり、不安を解消したりするための取り組みです。売り手市場では、求職者は内定を複数社から出される傾向があり、内定を出しても自社に入社してもらえないケースがあります。内定者面談を通して、入社後の流れや具体的な業務内容、期待していることなどを伝えると、内定者が「この企業で働きたい」という気持ちを高める効果が期待できます。
面接とは何か
面接の定義と目的
面接は、応募書類からは判断できない求職者の人柄やコミュニケーション能力を知るために実施します。主導権が企業側にあり、求職者の発言の自由度が制限されやすいのが特徴です。
企業が面接を実施する目的には以下の3つがあります。ここでは具体的な理由について解説します。
・求職者の適性を知る(スキル・人柄)
・求職者の志望度を高める
・ミスマッチを防ぐ
求職者の適性を知る(スキル・人柄)
求職者が自社で働く適性があるかを知るために面接を実施します。ここで言う適性とは、自社で業務をこなすスキルを持っているか、社風に合った人柄かなどです。
新卒採用であれば、求職者の仕事に対する価値観や熱意、ストレス耐性、コミュニケーション能力などを重点的に確認します。中途採用であれば、これらに加えて前職・現職の企業で培ったスキルや知識について聞き出し、自社で活躍できる能力があるかを見極めます。
ただし、数十分の面接だけで求職者の本音を引き出すのは難しく、普段の思考や行動と面接での姿にギャップが生まれかねません。求職者の緊張をほぐし、行動や心境に焦点を当てて話を深掘りすると、本音を引き出しやすくなります。
以下の資料は、面接で応募者を評価する際に使用できる面接評価シートです。
基本を押さえつつ、カスタマイズしやすい面接評価シートの採用サロンオリジナルサンプルとなっておりますので、よろしければダウンロードしてご活用くださいませ。
求職者の志望度を高める
面接には、求職者の志望度を高める目的もあります。自社で獲得したいと思う人材は、競合他社にも魅力を感じ、選考を受けていると考えるべきです。最終的に自社を選んでもらうためにも、面接を通して自社の魅力を伝えたり、求職者の不安を解消したりして、志望度を高める必要があります。
リクルートマネジメントソリューションズの「2023年新卒採用 大学生の就職活動調査」によれば、求職者の志望度が上がった出来事として「面接官が大きくリアクションをしてくれて安心して話せた」「面接が始まるときに緊張をほぐす声がけをしてくれた」「オンライン面接中にカメラを通して社内の雰囲気を見せてくれた」などが挙げられています。
一方で、志望度が下がった理由として面接官の対応の悪さが挙げられています。企業側は、面接が求職者の志望度を左右すると理解した上で、魅力の発信や不安解消など自社を選んでもらうための対応が必要です。
ミスマッチを防ぐ
面接の目的は、入社後の業務内容や社内の雰囲気などを伝え、入社後のミスマッチを防ぐことです。入社後のミスマッチによる早期離職が起こると、採用にかかったコストの損失につながります。
入社後のミスマッチが起きる原因として、面接時に伝えている情報量が少ない、求職者の情報を引き出せていないなどが挙げられます。
ミスマッチを防ぐため、企業の良い側面と悪い側面の両方を正直に伝えるようにし、書類の内容を深掘りして求職者の情報をできるだけ多く聞き出します。
面接の3つの種類
個人面接
個人面接は採用プロセスの中で最も重要な一環です。この面接では、候補者のスキルや経験を重点的に評価します。
個人面接は一対一のコミュニケーションの場でもあるため、候補者と面接官との相互理解を深めやすいのが特長です。これにより、候補者が会社のビジョンや目標をより深く知ることで、志望度を高めるきっかけともなり得ます。
集団面接
集団面接は複数の候補者を同時に面接する選考形式です。通常、企業側も複数の面接官が同席する場合が多く、複数対複数のコミュニケーションを取ることになります。
この形式は企業が多くの候補者を効率的に選考できる利点があります。逆に候補者にとっては、同じ質問に対する回答を競合者と比較しながら行うため、自己アピールのポイントをより明確にする機会になります。
しかし、緊張感や競争意識が高まるため、個人面接と比べてリラックスして臨むことが難しい点は注意が必要です。
オンライン面接
オンライン面接は採用活動において、近年ますます重要性を増しています。これは企業側と候補者が共に、場所を問わずに面接を行うことができる手段です。リモートワークの増加や選考の効率化を図るため、多くの企業が採用しています。
候補者にとっても、効率的に面接を受けることができ、また、自宅で参加することも多いため、比較的リラックスして参加できる点がメリットであると言えます。
オンライン面接の際に意識するべきなのは、適切なカメラの位置やネットワーク環境の確保です。これらの環境は、相手に与える印象に大きな影響を及ぼします。
面談と面接の違い
採用活動において、面談と面接はよく取り違えられることがありますが、最大の違いは合否の決定があるかどうかです。
面談は候補者と企業側がお互いの相互理解を深めるための場であり、自己紹介や会話を通じて雰囲気や相性を確認します。この際、合否を出すことはしません。
一方で、面接は具体的な質問や回答を通じてスキルや経験を評価します。面談と異なり、合否を決定することが目的です。
これまで企業の採用活動では面接のみを行い、合否を判断することが中心でしたが、近年では面談を実施する企業が増加しています。
理由として、採用活動が激化していることが考えられます。これまでのように求人を出せば採用できる、ということは無くなっています。
これにより、いかに候補者を動機づけするかが重要になってきたのですが、企業の魅力のうち「風土」や「文化」、「人的魅力」などを言語的に表現するのは限界があります。
そのため、面談を通じて候補者と採用担当者がコミュニケーションを取り、非言語情報を交換することによって互いに深く理解することが重要視されるようになってきています。
面談を実施するメリット
入社後のミスマッチを減らす
前述した通り、面接は応募者のスキルや経験を確認し、合否を判断する一方で、面談は相互理解を深める場です。
このような役割を持つ面接と面談を適切に使い分けることで、採用後のミスマッチを減らすことができます。面接では具体的な能力を見極めつつ、面談では候補者と企業の相性や文化への適合性を評価します。
このバランスの取れたアプローチは、入社後の適合度を高め、採用後の円滑な適応を促進します。採用活動において、面接と面談の使い分けは、候補者と企業の間における相互理解を深め、採用の成功をより確実なものにします。
潜在層にアプローチできる
面談はフラットに企業と候補者が会話することができる場であるため、候補者も面接や説明会と比較して気楽に参加することができます。
そのため、そこまで志望度が高くない状態である候補者や、就職活動における情報収集フェーズの候補者とも接点を持つことができます。
結果としてアプローチできる候補者層が増え、母集団形成に大きく役立ちます。
この時に重要なのは、候補者は様々な理由で座談会に参加することが考えられるため、それぞれの参加理由や志向に応じて企業側も対応を変えていく必要があることです。
成功する面談のポイント
候補者に合わせた面談者を選定する
面談の成功には、適切な面談者の選定が鍵を握ります。候補者の特性や志向に合わせて、相性の良い面談者を選ぶことが重要です。
面談者は候補者との相互理解を促進し、積極的な情報交換が可能である人材を選定します。
例えば、候補者が技術的な側面に関心がある場合、それに精通した技術面談者が有効です。
また、個人的な志向やキャリアに合ったアドバイスができる面談者を選ぶことも重要です。
面談者と候補者の相性が良ければ、より有意義な面談が実現し、採用活動の成功につながります。成功する面談を行うためには、候補者にフィットした適切な面談者を選定することが不可欠です。
面談で話す内容を準備しておく
面談は候補者との双方向のコミュニケーションであるため、企業が面談を成功させるためには、面接官側も事前に面談でどのような情報を伝えたいのか、候補者にどんな質問をしたいのかを準備することが大切です。
候補者の適性を見極めるための質問や、候補者にとっても重要な情報を伝えるための内容を整理しましょう。また、企業の魅力や求める人材像なども明確にすることが重要です。
これによって、双方が有意義なコミュニケーションを図り、ミスマッチを防ぎながら、相互の理解を深めることが可能になります。
そのため、企業が面談を成功させるためには、準備と計画をしっかりと立て、候補者とのコミュニケーションを円滑にすることが大切です。
まとめ
本記事では、面談と面接の違いについてご紹介してきました。近年の採用活動の激化により、企業は選ぶ立場から選ばれる立場へと変わっています。
そのため、いかに企業の魅力を余すことなく伝えていくかが採用成功において重要となっています。
ここで、候補者が転職の際に企業に対して感じる魅力は、以下の8つのカテゴリーに分けることができます。
● 理念・ビジョン(企業姿勢)
● 戦略の将来性(経営基盤)
● 仕事の醍醐味(仕事特性・成長・キャリア)
● 競争優位性(事業・商品)
● 風土の親和性(組織風土)
● 人材・人間関係(人的資産)
● 職場環境(人事施策)
● 制度・待遇(報酬・待遇)
この8つの魅力の中で、「風土の親和性(組織風土)」と「 人材・人間関係(人的資産)」を言葉や図、絵で伝えるのは難易度が高く、求人原稿で表現するには一定の限界があります。
そのため、対面でのコミュニケーションを取ることができる面談や面接という場において、これらの魅力を非言語的に伝えていくことが大切です。
クイックでは、そんな採用成功の鍵を握る面談や面接を成功させるため、『面接官トレーニング・リクルーター研修』をご用意しております。
こちらの研修では、求職者のタイプを分類した上でそれぞれに適したコミュニケーションを取ることを軸に、面接成功の方程式をご共有しております。
内容としては、面接官の心構えや面接ルール、話し方の座学とロープレを交えた実践的な内容になっております。
候補者の理解の仕方や魅力付けの仕方など、課題に応じたプログラムを複数ご用意しておりますので、気になる企業様はぜひ、お問い合わせくださいませ。
面接官トレーニング・リクルーター研修 | クイックの採用サロン
無料ダウンロード
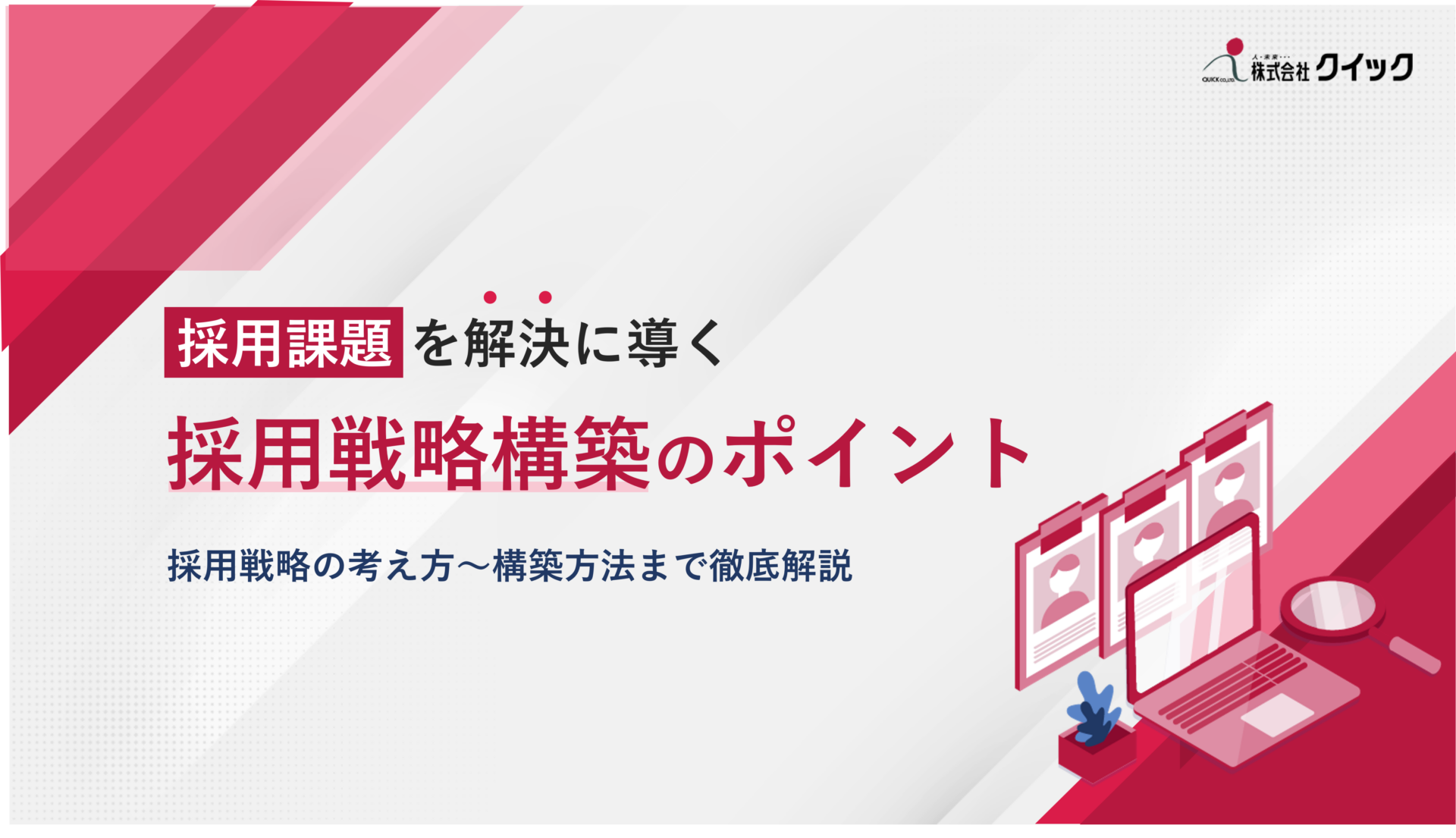
採用課題を解決に導く採用戦略構築のポイント
採用活動においても、パフォーマンスの要となるのは「戦略」の設計です。 コンサルティングサービス「採活力」は、貴社に最適な採用コミュニケーションを設計し、採用活動を成功へと導きます。
セミナー情報

あわせて読みたい