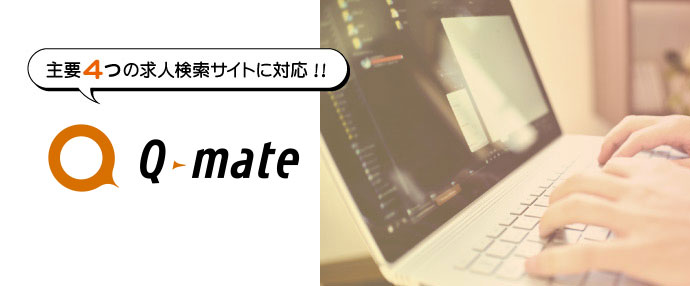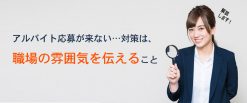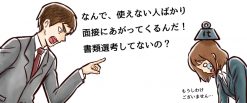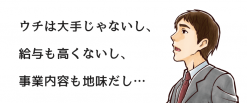中途入社者が定着しない理由
転職が当たり前の世の中になっている昨今、転職を繰り返す中途入社者も珍しくありません。ここでは、中途入社者の離職理由や入社後にとまどうポイントランキングを紹介します。
厚生労働省調査に見る中途入社者の離職理由
中途入社者における前職の離職理由を雇用動向調査で確認します。
男性では、「給与等収入が少ない」が7.4%で最も高く、次いで「人間関係が好ましくない」が7.1%、「労働時間・休日等の労働条件が悪い」が6.6%、「会社の将来が不安」が6.1%と続いています。他方、女性では、「労働時間・休日等の労働条件が悪い」が10.3%と最も高く、次いで「人間関係が好ましくない」が8.9%、「給与等収入が少ない」が6.6%、「会社の将来が不安」が5.2%と続く結果となりました。
このように、男女別では1位と3位に入れ替わりがありますが、離職理由の上位は、双方、同一の理由となっていることがわかります。
離職率について詳しく知りたい方は、「自社の離職率は平均より高い?主な原因と離職率を下げる方法」の記事をご参考ください。
(※参考)厚生労働省:「令和3年上半期雇用動向調査結果の概況」
中途入社者が入社後にとまどうポイントランキング
株式会社リクルートキャリアの調査によると、「中途採用をしてもすぐ辞めてしまう」といった悪循環の原因は、中途入社者が入社後にとまどう「職場の習わし」にあると解説しています。
この「職場の習わし」とは、自社の従業員が当たり前に使っている業界用語や社内用語、独自ルールや慣習など、自社の従業員であれば当たり前に知っていることです。しかし、異文化の企業から転職してくる中途入社者は、この職場の習わしにとまどい、離職に至るケースが多いものと考えられます。
この中途入社者の入社後にとまどう理由ランキングは次のとおりです。
- 【1位】前職との仕事の進め方ややり方の違い(45.5%)
- 【2位】社内や業界用語等、専門知識が分からない(31.1%)
- 【3位】職場ならではの慣習や規範になじめない(24.6%)
- 【4位】仕事内容やミッションが考えていたものと違った(19.2%)
- 【5位】教育・トレーニング、研修環境が整っていない(17.1%)
- 【6位】離職する人が多い(15.0%)
- 【7位】入社後のキャリアパスが描きづらい(14.0%)
- 【8位】勤務時間、休日休暇等が考えていたものと違った(12.1%)
社会人経験があることから、「知っていて当たり前」「できて当然」という先入観から、周囲からフォローされないことが多くあります。しかし、こうした「職場の習わし」までも知っている、あるいは教える必要はないと扱われることも珍しくありません。
(※参考・引用)株式会社リクルートキャリア「中途入社後活躍調査(2018-2019)」「2019年トレンド予測 中途採用領域」
中途入社者が定着しない大きな損失3つ
中途入社者が定着しないと、負のスパイラルに陥り、企業に大きな損失をもたらします。ここでは、中途採用者が定着しないと生じる大きな損失3つを解説します。
現場社員の負担増
一つ目は、現場社員の負担増です。
社会人経験のある中途入社者であっても、教育は不可欠です。ビジネスの基本は押さえていても、特有事項である業界や取引先の状況、職場の習わしを教えるなどのサポートは欠かせません。
しかし、労力をかけた中途入社者が定着しない環境では、新しい人材が来るたびに教育をし続けなければならず、現場社員の負担を増大させてしまいます。こうした環境に嫌気をさし、現場社員が離職してしまうリスクもあるでしょう。
採用コストの増大
二つ目は、採用コストの増大です。
中途入社者が辞めるたびに、欠員補充するための広告コストや人材紹介手数料など、採用コストが発生します。特に中途採用は、人材紹介手数料が理論年収の30~35%と高額であることから、新卒の採用コストより高い傾向にあります。
また、早期離職傾向が高まるほど、戦力化できずに退職することになり、投資回収ができない状況に陥るリスクが高くなる恐れがあります。
採用力の低下
中途入社者が定着しないことは、離職率が高まることを意味します。
離職率は、青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)において、新卒採用をする企業全てに情報提供義務が課されています。具体的には、「過去3年間の新卒採用者数・離職者数」が対象となっており、Webサイトや求人票、会社説明会などによる情報提供が求められているのです。
中途採用においても、求職者はこの離職率の情報にアクセスすることが可能なため、離職率が高い企業は敬遠され、採用力の低下につながるリスクがあります。
【フェーズ別】定着率を向上させるポイント
定着率を向上させるポイントには次の3段階あります。
- 求人募集フェーズ
- 選考フェーズ
- 入社後フォローフェーズ
今から順番に解説していきます。
1.求人募集フェーズ
仕事内容を明確にする
入社後の仕事内容は、求人募集の段階で、できるだけ具体的に示すようにしましょう。
中途入社者は、これまでの経験を踏まえて新しいキャリアを築きたいと考えることが大半です。
そのため、中途入社者のイメージと実際の仕事内容に、極力ミスマッチが生じないよう心がける必要があります。
そして大事なことは、良い面と悪い面の両面を包み隠さず伝えることです。採用したい一心で、悪い面を伝えないケースもあると思われますが、後々、採用ミスマッチを生み出す原因になり得ます。
悪い面も伝えることで、短期的には入社者を減らすリスクもあるでしょう。しかし、長期的にはミスマッチによる早期離職を防ぐことができます。
必要なスキルを丁寧に表記する
必要なスキルは、現場の部門から正確に確認する必要があります。特に、「必須のスキル」「あると望ましいスキル」を明確に区分してもらうようにしてください。
この区分ができていないと、「全てのスキルがないと応募できない」「本当に必要なスキルをもつ求職者から応募がない」という事態が生じるリスクがあります。
いざ現場に配属されたら、「スキル不足で活躍できない」といったことがないように、必要なスキルは丁寧に記載してください。
安易な未経験歓迎は早期離職のもと
人材不足を背景に、応募のハードルを下げることもあるでしょう。しかし、安易な条件緩和は採用ミスマッチを引き起こす原因となります。
教育体制が整っていて、未経験でも難易度が高くないポジションであれば「未経験歓迎」を訴求することは有効です。
しかし、「必須スキルの難易度が高い」「教育体制が整っていない」といった場合は、実態に合わせた要件を記載すべきです。
待遇は正確に表記する
休みとお金に関わる部分については、特に注意が必要です。
実際に提示される条件と求人情報との差異に、求職者は敏感になるため、たとえ、その差が取るに足らないものだとしても、その事実は会社への不信感として、求職者の心に残ってしまいます。
ハローワークで募集する場合は特に注意
無料で求人できるメリットはありますが、写真を掲載できない、求人票に記載できる情報が少ないなど、入社後のミスマッチが起こりやすいこともあります。
足りない情報については、求人募集フェーズで会社説明会を実施するか、次の選考フェーズで補足説明してください。
2.選考フェーズ
面接で直属の上司と引き合わせる
性格や雰囲気、相性などが合わないということは、どうしても起こり得ます。
仕事で関わる上司やリーダークラスの方には、ぜひ面接に参加してもらうようにしてください。
仕事に対する価値観など、今後、現場で活躍できる人材かを見極めてもらうことが可能です。
また、専門的なポジションを想定している場合、必要なスキルや知見があるかを確認しておくことで、ミスマッチを防ぐこともできます。
社内見学やメンバーとの顔合わせを行う
選考段階に、社内見学を実施できるとベターです。製造業であれば工場見学を実施すると、製造職や開発職希望者の入社意欲を高めることも可能です。
さらに、内定出し後から内定承諾前の段階で、メンバーと引き合わせることも有効です。これにより、入社後のイメージを具体的に持てることで、求職者の不安を解消できることが大きなメリットになります。
職歴の確認
職歴が多い人については、退職理由を丁寧にヒアリングしてください。
前職がブラック企業でやむを得ず早期離職している場合も、VORKERSや転職会議のような会社の評判を調べられるサイトで検索すれば、ある程度は、情報の裏付けが取れる可能性があります。ただし、必ずしも信憑性が高いとはいえませんので、参考程度に留めてください。
適性検査の活用
適性検査とは、求職者の組織や職務に対する適性や、組織に対する価値観、職業能力を客観的に図る手段のひとつです。
基本的な学力や知的能力のほか、価値観、人間性、性格など、さまざまな特性や能力を定量化するため、企業が定める採用基準や求める人物像をスクリーニングすることが可能です。
特に、中途入社者に定着してもらうために重要な項目は「価値観」です。従業員の主体性を重んじる企業では、保守的な価値観をもつ求職者はミスマッチになるでしょう。ワークライフバランスを重視する求職者は、責任感を重んじる企業には合いません。
このように、自社の求める人材像や価値観と合う人材をスクリーニングするために、適性検査を活用することも有効な手段です。
適性検査については、別の記事で詳しく解説しています。
採用試験で適性検査の活用を検討中の方は、ぜひご一読ください。
適性検査の内容と選び方!採用のプロが解説【23種類の一覧付き】
RJPで採用ミスマッチを減らす
RJP(リアリスティックジョブプレビュー)を採り入れることで、採用ミスマッチを防ぐことが可能です。
このRJPとは、入社前に、仕事や職場の実態をありのままに伝えることで、入社後に受けるギャップを緩和する試みを指します。近年、この手法を採り入れる企業が増えてきています。
仕事の厳しさや社風についてオープンにすることで、より納得した状態で入社してもらうことができます。
もちろん、ありのままの状態を伝えることで、選考辞退が増える可能性はあります。
ただし、入社後に合わなくて早期離職になるよりも、企業と求職者双方にとってミスマッチを防ぐことができるため、長期的には離職防止に大きく寄与するといえます。
3.入社後フォローフェーズ
即戦力にも、慣らし運転は必要
中途入社者が同業・同職種の転職であったとしても、いきなり仕事を任せて放置するのではなく、仕事に慣れるまでの慣らし運転期間は必ず設けるようにしてください。
資料の作り方ひとつとっても、会社が違えば職場の習わしは様々です。
中途入社者にとっては、前職と比べて仕事の裁量の範囲も異なるはずです。
そのため、中途入社者には、仕事の流れとともに、「前職との仕事の進め方ややり方の違い」「社内や業界用語等の専門知識」「職場ならではの慣習や規範」など中途入社者がとまどうポイントを丁寧に教えることで、とまどいを解消してもらう準備期間が必要です。
意図的に周囲との接点を作る
入社して間もないタイミングで、部署内やチーム内のメンバーとコミュニケーションをとれるよう、周囲との接点を作ることも、定着化に有効な施策です。
オフィス内に知らない人が多くいる状況は、少人数の組織であればあるほどストレスになります。周囲との接点を極力早めに作ることで、中途入社者は職場に早く打ち解けることができ、早期に活躍してもらうことが可能です。
チームメンバーでランチに行くなど、気軽に参加できる懇親の場を作ってあげるのもおすすめです。
今後、中途採用は、人材戦略においてますます重要になる
新卒一括採用。
石の上にも三年。
転職は恥。
こうした昭和の価値観が薄れ、スキルUPや待遇改善を目的に転職を繰り返す人が増えてきました。
第二新卒者を、新卒同様の処遇で迎え入れる企業も増えてきています。
かつては35歳が限界と言われた転職年齢もジワジワと上昇し、いまでは40代での転職も珍しくありません。
そんな中で、優秀な人材、事業にとって必要な人材を確保し続けるためには、いかに中途採用を成功させるかが重要です。
今回ご紹介した内容を、1つでも2つでも実践いただき、企業と求職者の素敵な出会いがたくさん生まれることを願っています。
無料ダウンロード
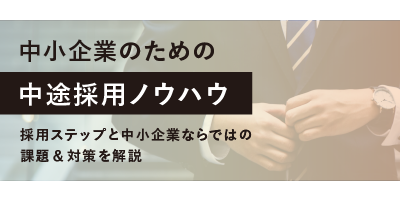
中小企業のための中途採用ノウハウ
採用活動を「採用計画」「求人募集」「選考実施」の3フェーズに分け、中小企業における採用戦略ポイントを解説。さらに、よくある課題と解決につながる採用手法も併せてご紹介。
無料ダウンロード
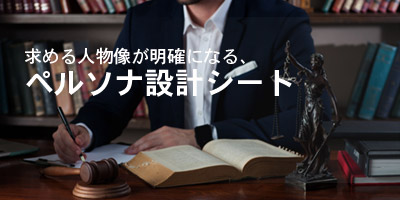
無料ダウンロード
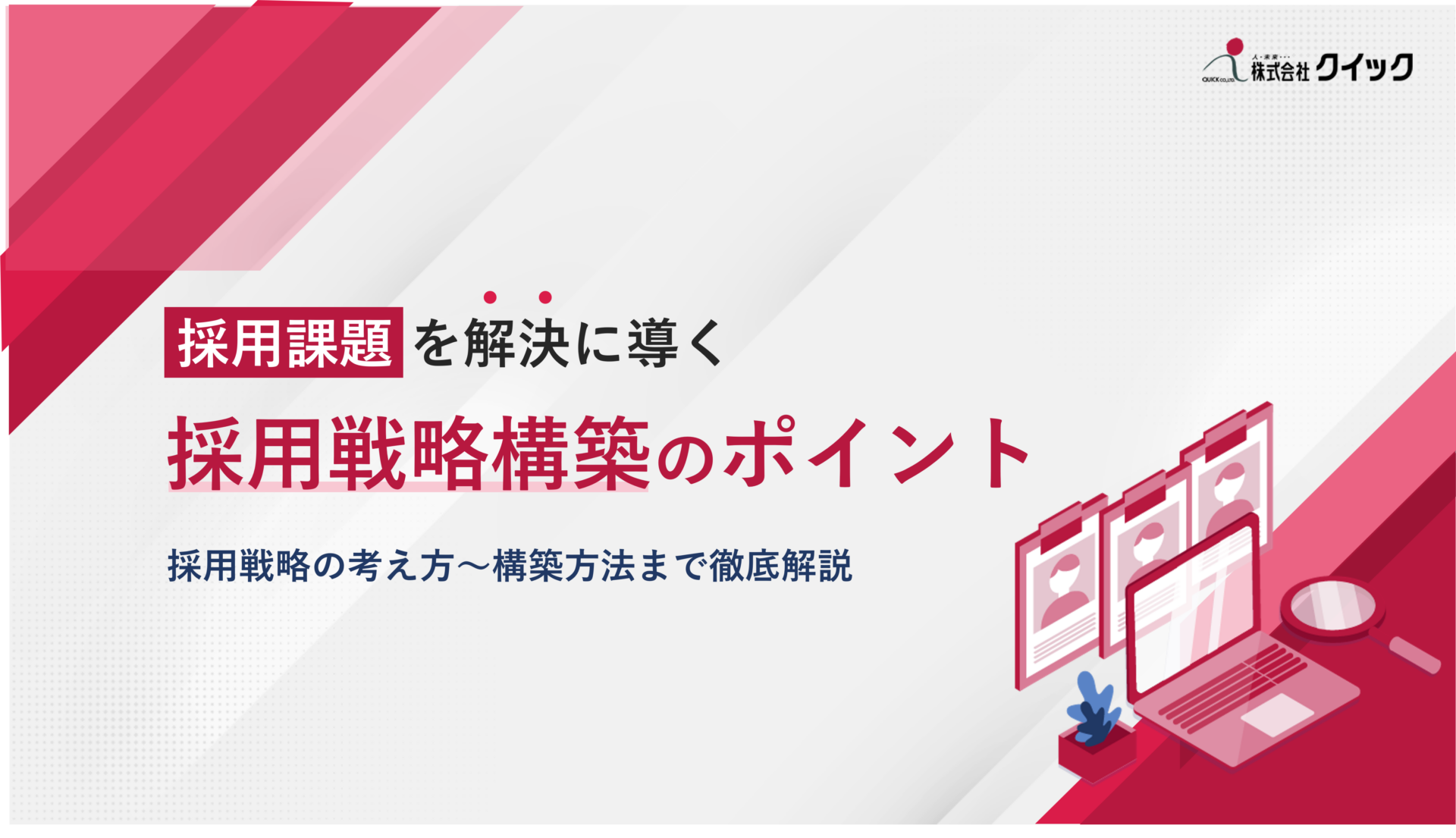
採用課題を解決に導く採用戦略構築のポイント
採用活動においても、パフォーマンスの要となるのは「戦略」の設計です。 コンサルティングサービス「採活力」は、貴社に最適な採用コミュニケーションを設計し、採用活動を成功へと導きます。
セミナー情報

あわせて読みたい