オンボーディングの意味やメリットとは?
転職する傾向が強まってきていることを背景に、新卒社員だけでなく中途入社社員に対してもサポートするオンボーディングが注目されています。ここでは、オンボーディングの意味とメリットについて解説します。
新しく入ってきた人材が馴染めるようサポートする仕組み
オンボーディングとは、新卒、中途で入社した新入社員や他の部署から異動してきた社員がいち早く馴染めるように社内全体でサポートする取り組みです。オンボーディングの具体的な取り組みとして以下が挙げられます。
・新メンバー歓迎会の実施
・社員同士の交流のための社内イベントの実施
・会社の風土や独自のルールを伝えるための資料の配布
・入社後のギャップを少なくするためのインターンや入社前研修の実施
・業務に慣れるためのOJTの実施 など
オンボーディングと新人研修の違い
オンボーディングと新人研修は混同されがちですが、両者には違いがあります。異なるポイントは、対象社員と実施期間、内容です。2つの特徴を以下の表にまとめました。
| 新人研修 | オンボーディング | |
|---|---|---|
| 対象社員 | 新卒社員 | ・新卒社員 ・中途社員 ・異動してきた社員 |
| 実施期間 | 1か月程度 | 数か月~1年程度 |
| 内容 | ・オリエンテーション ・業務紹介 ・ビジネスマナー研修 など |
・歓迎会 ・社内イベント ・オリエンテーション ・業務紹介 ・ビジネスマナー研修 ・OJT など |
新人研修の対象は新卒社員です。中途入社の社員や異動してきた社員は即戦力であると考えられているため、新人研修の対象とはなりません。一方でオンボーディングでは、中途社員と異動してきた社員も人間関係の構築や業務理解などにサポートが必要と判断され、対象となっているのが一般的です。
新人研修が入社後1か月程度の短期間でオリエンテーションや事業説明をするのに対し、オンボーディングは数か月から1年という中長期的な期間でさまざまな取り組みを実施します。継続的にサポートすることで、戦力化までの期間を少しでも短くする狙いがあります。
オンボーディング実施の2つのメリット
オンボーディングは、新入社員の早期離職防止や他部署から異動してきたメンバーを早く戦力にするために有効な取り組みです。それぞれのメリットについて解説します。
【1】早期離職防止につながる
オンボーディングの実施は、早期離職の防止に効果的です。新入社員が早期離職する主な原因は、人間関係のトラブルや業務内容・職場環境への不満です。オンボーディングは、新入社員が既存社員との仲や業務内容の理解を深めるのに役立ち、早期離職につながる不満の解消が期待できます。
例えば、ランチ会は人間関係をうまく築けない悩みを解消するのに有効です。新入社員は、上司や既存社員とのコミュニケーションの取り方が分からず、話しかけづらい悩みを抱えています。ランチ会を通して新入社員は既存社員の人柄を理解でき、コミュニケーションを取りやすくなります。さらに、業務以外の面での相談もしやすくなると、新入社員のストレスや不満の解消にも有効です。
新入社員の早期離職を防ぐためには、ランチ会以外にも入社前インターンシップの実施や業務のコツをまとめた資料の共有などのオンボーディングの取り組みを実施し、新入社員の不安・不満の解消することが重要です。
【2】新メンバーが早く戦力になる
オンボーディングは、新入社員や異動してきた社員などの新メンバーが業務や企業独自のルールを覚えやすくなり、早く戦力として成長してもらうことに有効です。
新卒社員はもちろん、即戦力と思っていた中途入社の社員も、業務の流れや企業独自のルールを覚えるのに時間がかかり、即戦力とならない場合があります。
例えば、オンボーディングの取り組みの一環として、事前に業務の流れやルールを記載している資料を共有しておき、分からないことはすぐに周りの社員に質問してもらうように新メンバーに知らせておけば、業務理解にかかる時間の短縮が期待できます。
オンボーディング実施の流れ
オンボーディングは以下の流れで実施します。オンボーディングの取り組みが成功するためのポイントについてそれぞれ紹介します。
【1】最終目標達成のための細かい目標を設定する
【2】具体的な育成プランを作成する
【3】プランに沿って施策を実行する
【4】振り返りを行う
【1】最終目標達成のための細かい目標を設定する
オンボーディング実施後の新メンバーに期待する姿を最終目標として決定し、そこから逆算して最終目標達成のための細かい目標を設定します。
例えば、「新入社員が一人で営業できるようになる」という大きな目標を設定したとします。大きな目標だけ設定していると、新入社員が業務の段取りや見積もりの作り方などが身に付けられずに自分のやり方で進めてしまい、予算オーバーやスケジュール崩れ、関係部署との関係悪化などの問題が発生する可能性があります。
オンボーディング実施後に、必要なスキルを身に付けられていない事態を防ぐためにも、いつまでにどんなスキルを身に付けるべきか、人間関係のあるべき姿などの細かな目標を、大きな目標から逆算して設定することが重要です。細かな目標は1年を目安に、加入後2週間、1か月、3か月、半年、9か月というように期間を区切って設定するのがおすすめです。
【2】具体的な育成プランを作成する
細かな目標を達成するための具体的な育成プランを作成します。例えば、新卒社員が入社1週間で企業理念について理解できるように社長や役員からの講義を実施する、中途採用者が1か月以内にチームに馴染めるように歓迎会やランチ会を実施するなどの取り組みが挙げられます。また、自社の業務に必要なスキルを身に付けてもらうためにOJTを実施するという手も有効です。
具体的なプランを作成したら、現場の社員と内容をすり合わせることが重要です。作成側と現場の社員とでは課題や身に付けさせるべきスキルの認識にズレがある可能性があります。現場からのフィードバックをもらって改善すれば、オンボーディングの取り組みの成功が期待できます。
【3】プランに沿って施策を実行する
作成したプランに沿って、オンボーディングを実施していきます。オンボーディング担当者は中長期的な取り組みであることを頭に入れておき、少しずつ新メンバーが目標を達成できるようサポートしてください。プランがうまく機能していないと感じたら、改善できそうなポイントやうまく機能していない理由などのメモを取り、次回以降の改善につながります。
また、オンボーディングを効率的に実施するためには教育体制の整備が重要です。教育担当者にすべて任せていると、教育担当者の負担が増えて業務に支障が出る上に、新メンバーに対する教育に手が回らない可能性があります。職場全体で新メンバーをフォローする教育体制を整備してください。
【4】振り返りを行う
細かな目標ごとに振り返りを実施すると、施策の効果測定ができる上に改善点の発見にもつながります。事前に評価指標を設けた上で、受け入れ側である教育担当者や配属部署のメンバーと新メンバー両方からの意見を聞くと、改善に役立つ意見を集めやすくなります。見つけた課題からPDCAサイクルを回し、オンボーディングを自社に合ったより良いものにしてください。
オンボーディングを実施している企業事例
オンボーディングを実施している企業の具体的な取り組みを紹介します。企業規模や業種によって効果的な施策は異なるため、紹介する例を参考に自社に合ったオンボーディング施策を考えてください。
LINE株式会社
LINE株式会社で実施しているオンボーディングの取り組みは、新入社員の不安や疑問を解消するために、LINEを使って分からないことを何でも聞ける「LINE CARE」という社内サービスです。総務やITなどのバックオフィス部門の社員で構成されており、すぐに答えられる質問であればメンバーが回答し、答えられない質問は必ず担当者につないで疑問を解消できるようにしています。また、オフィス内にもLINE CAREのサービスカウンターを設置しており、直接質問することも可能です。
株式会社メルカリ
株式会社メルカリでは、新型コロナウイルス感染拡大を受けて完全リモート入社に移行しており、リモートでのオンボーディングを実施しています。その中でも、エンジニア向けに実施しているオンボーディングの取り組みを紹介します。
| 取り組み | 取り組みの目的 |
|---|---|
| エンジニア向けオリエンテーション | メルカリのエンジニアリングの視点を伝えて、組織への理解を深めるため。 |
| オンボーディングポータル | 気軽に質問するのが心理的に難しいリモート入社のメンバーが、必要な情報をいつでも見られるようにするため。 |
| メンター制度 | 知識豊富なエンジニアをメンターにし、すぐに実務に取りかかれるようにするため。 |
| リモートランチ会 | 新メンバーの横のつながりを広げるため。 |
| 進捗確認 | オンボーディングの状況を可視化し、新メンバーに対して適切なサポートをするため。 |
中でもメンター制度とリモートランチは、定期的なコミュニケーションの機会となっており、新メンバーのコミュニケーションに関する不安払拭に役立っています。
株式会社コンカー
株式会社コンカーで実施しているオンボーディングは、ウェルカムランチやメンター制度といった基本的な取り組みに加えて、新メンバーが他部門のメンバーとのコミュニケーションを取りやすくするための以下2つの取り組みです。
・部署や役職を超えてコミュニケーションを取るバディ制度
・他部門メンター制度
この2つの制度により、他部門のメンバーとの関係構築を手助けし、新メンバーの視野を広げることに役立っています。
また、絆ミーティングという、社長が社歴の長い社員と対談するオンラインミーティングも実施しています。会社の歴史や社員のプライベートな面を伝え、新メンバーの社内情報のキャッチアップに効果的な取り組みです。
まとめ
オンボーディングとは、新卒、中途で入社した新入社員や他の部署から異動してきた社員がいち早く馴染めるようにサポートする取り組みです。新入社員の早期離職防止や新メンバーの即戦力化が期待できます。ただし、オンボーディングは中長期的な取り組みです。実施してすぐに効果が出るとは限らないため、課題を見つけながら改善に努めてください。
無料ダウンロード
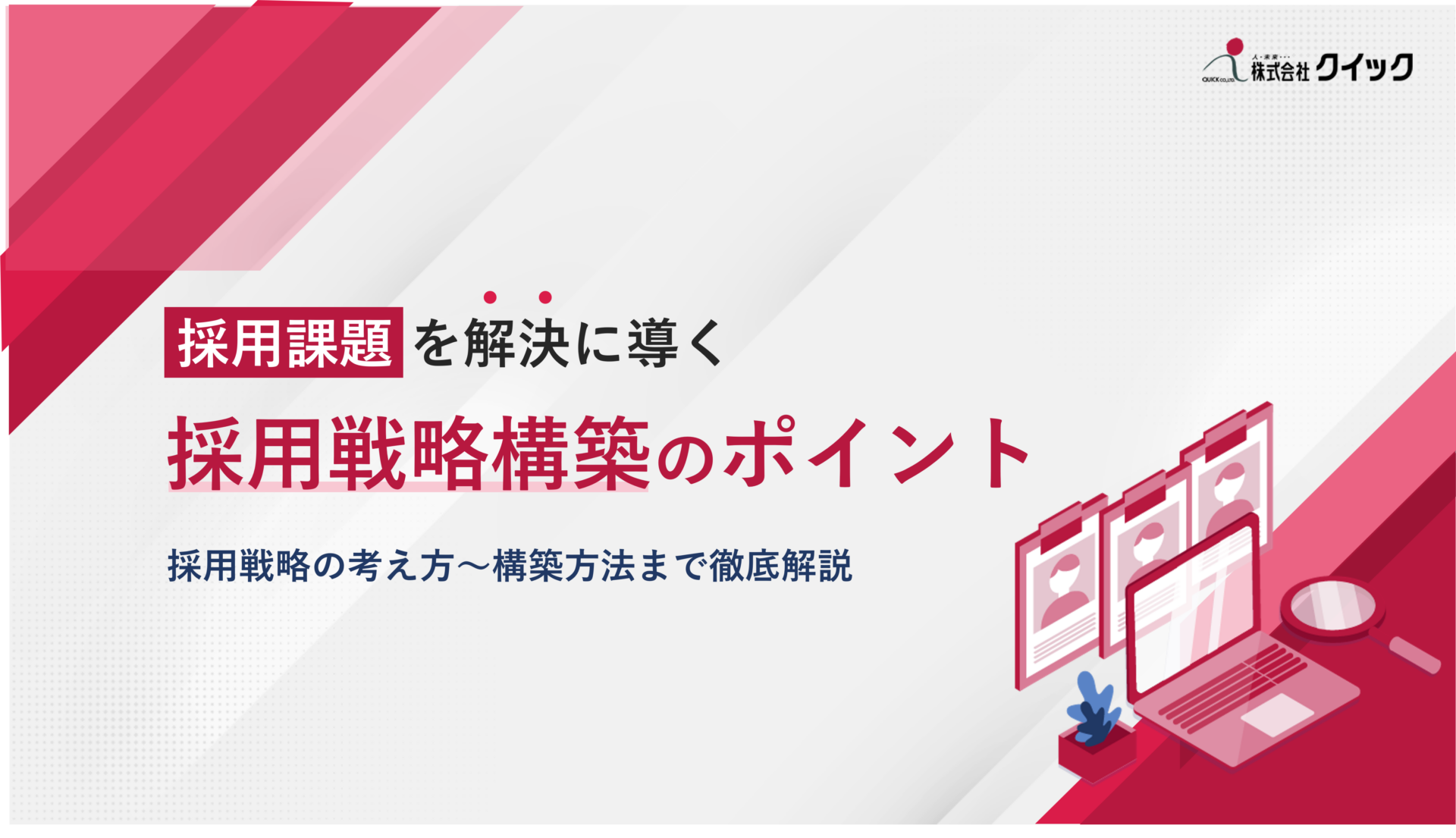
採用課題を解決に導く採用戦略構築のポイント
採用活動においても、パフォーマンスの要となるのは「戦略」の設計です。 コンサルティングサービス「採活力」は、貴社に最適な採用コミュニケーションを設計し、採用活動を成功へと導きます。
セミナー情報

あわせて読みたい









