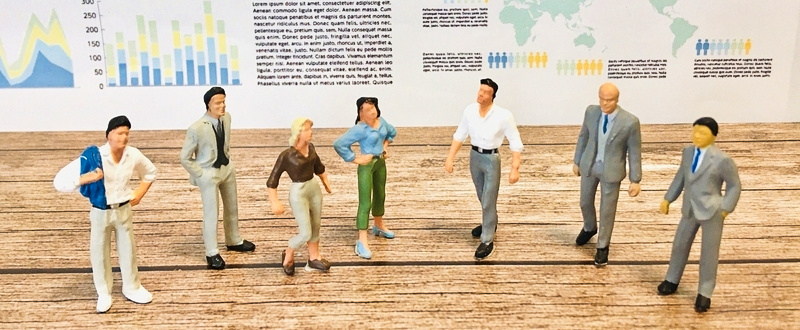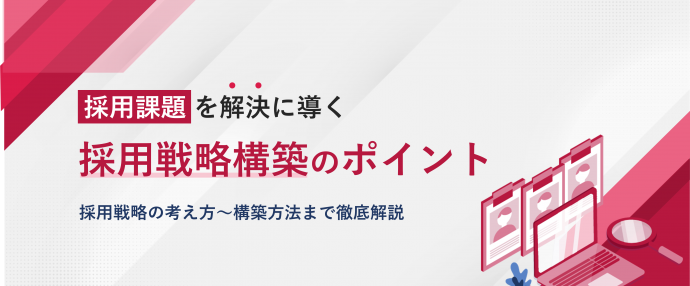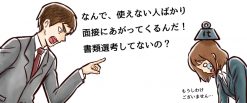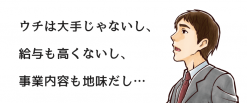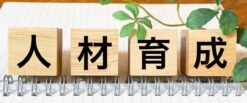ダイバーシティ&インクルージョンとは?
ダイバーシティ&インクルージョンは、「ダイバーシティ=多様性」と「インクルージョン=受容」を組み合わせた考えです。企業におけるダイバーシティ&インクルージョンの活動や注目される背景について紹介します。
多様な人材が活躍できる場を作る活動
ダイバーシティ&インクルージョンとは、組織において多様性を重視し個々の違いを受け入れたうえで、組織の活動にその違いを生かしていこうという考え方です。この考え方を企業内に浸透させることによって、国籍や人種、年齢、性別などが異なる多様な人材が集まる組織で、お互いを受け入れながら成長し、新たなサービスや価値を創造できます。女性活躍推進やシニア層の活用などが、ダイバーシティ&インクルージョンの代表的な取り組みとして挙げられます。
ダイバーシティ&インクルージョンが注目される背景
日本においてダイバーシティ&インクルージョンが注目される背景には、少子化によって労働人口が減少し、幅広い層から労働力を確保する必要性が出てきたことが挙げられます。幅広い層から労働力を確保するためには、高齢者や障がいを持つ人などの多様な人材を活用する考え方(=ダイバーシティ)と、それらの人材の能力が発揮できるように組織の一体感を生み出す取り組み(=インクルージョン)の両輪が必要となります。そのためダイバーシティ&インクルージョンという概念が広がっていきました。
さらには、消費者ニーズの多様化もダイバーシティ&インクルージョンの促進が求められる要因の一つです。従来の働き手だけでは多様化した社会のさまざまなニーズに対応できず、企業としての競争力も低下してしまいます。こういった課題への対策として、社内に多様な価値観や考え方を持つ人材を雇用する動きも見られます。
ダイバーシティ&インクルージョン推進のメリット・デメリット
社会要請や企業のイノベーションを図るために重要なダイバーシティ&インクルージョンの推進。ここでは、ダイバーシティ&インクルージョン推進におけるメリット・デメリットを解説します。
ダイバーシティ&インクルージョン推進3つのメリット
ダイバーシティ&インクルージョン推進のメリットを次のとおり説明します。
- 【1】優秀人材の確保
- 【2】イノベーションの創出
- 【3】企業イメージの向上
【1】優秀人材の確保
ダイバーシティ&インクルージョン推進における最大のメリットは、優秀人材の確保ができること。ダイバーシティ&インクルージョンの推進によって、性別や年齢、国籍、障がいの有無にかかわらず、誰もが多様性を認め合い、能力を発揮できる職場環境を実現できます。こうした環境を整えることで、優秀な人材確保につなげることが可能です。
【2】イノベーションの創出
イノベーションの創出につなげられることも、大きなメリットです。
同質の価値観を持った集団では、新たな発想が生まれにくく、イノベーションの創出が難しいこともあるでしょう。しかし、ダイバーシティ&インクルージョン推進によって、多様な価値観を取り入れられることはもちろん、それらの価値観を融合し、イノベーションの創出につなげることが可能です。
【3】企業イメージの向上
企業イメージの向上につながることも、メリットのひとつです。
多様性の取り組みが遅れている日本において、ダイバーシティ&インクルージョンを推進することにより、「先進的な企業」というイメージを訴求することが可能です。社会的評価の高い企業に属することで、従業員の帰属意識が高まり、エンゲージメントの向上も期待できるでしょう。
ダイバーシティ&インクルージョン推進3つのデメリット・課題
ダイバーシティ&インクルージョンは、さまざまなメリットをもたらしますが、推進するにあたって以下のようなデメリットや課題があります。
- 【1】ハラスメントの発生リスク
- 【2】組織内の混乱リスク
- 【3】待遇・評価の困難さ
【1】ハラスメントの発生リスク
多様な人材を受け入れることで、ハラスメントリスクが発生することもあります。
具体的には、組織内で多様性の理解が十分でない場合、摩擦や偏見が生じやすくなるほか、異なる価値観やバックグラウンドを持った者に対する抵抗感が起きやすいなどが挙げられます。こうしたリスクを避けるためには、ダイバーシティ&インクルージョン推進の目的を十分に説明し、ハラスメント防止教育を行うことが重要です。
【2】組織内の混乱リスク
ダイバーシティ&インクルージョン推進の過渡期には、組織内の混乱リスクが起きやすくなります。
「教育が十分でない」「偏見や先入観が拭えない」「抵抗を示す社員の存在」などから、組織内で対立や衝突が起き、混乱を招くことが考えられます。また、働き方の多様化がコミュニケーションやチームワークの低下をもたらすこともあるでしょう。こうした組織内の混乱を防ぐには、社員の意識改革とともに、コミュニケーションツールを整えるなど、環境整備をすることも大切です。
【3】待遇・評価の困難さ
人材の多様化によって、待遇や人材評価も複雑化しやすくなります。
個々の違いを尊重しながら働きやすい環境を提供するとともに、それぞれに適した人材評価の仕組みが必要になります。多様性を理解しつつ、一部の属性に配慮しすぎるなどの不公平が生じないようにすることが重要です。社員の意見や不満を吸い上げるなど、公平な待遇や人材評価を行いましょう。
ダイバーシティ&インクルージョンの主な取り組み5つ
ダイバーシティ&インクルージョンは、主な取り組みとして以下の5つが挙げられます。ここでは、それぞれの取り組みの内容やメリットなどを紹介します。
- 【1】女性が活躍できる環境整備
- 【2】障がい者の雇用促進
- 【3】外国籍人材の雇用促進
- 【4】シニア層の活用
- 【5】LGBTQへの配慮
【1】女性が活躍できる環境整備
ダイバーシティ&インクルージョンの代表的な取り組みとして挙げられるのは、女性活躍のための環境整備です。女性ならではの視点から新たな商品開発やサービスのアイデアが期待でき、消費者の多様なニーズにも対応しやすくなります。ダイバーシティ&インクルージョンを実践する企業では、女性管理職を増やす取り組みや結婚・出産後でも仕事を続けられるように、柔軟な働き方ができる制度の整備を実施しています。
2016年に施行された女性活躍推進法でも、常時雇用する社員が301人以上の企業に対して女性社員の活躍に関する状況や課題を把握し、その状況・課題を踏まえてより働きやすい環境を整備するための行動計画の提出を義務付けています。2022年4月1日からは、対象企業が101人以上の企業に拡大します。ただし、300人以下の企業は努力義務です。
【2】障がい者の雇用促進
ダイバーシティ&インクルージョンの取り組みとして、障がい者の雇用促進も挙げられます。障がい者雇用は労働力確保に加え、障がい者の視点からバリアフリーに配慮したオフィス・店舗づくりやユニバーサルデザイン商品の開発などを実施するときに大きな力となることが期待できます。ダイバーシティ&インクルージョンの一環として、企業によっては、障がい者の資格取得の支援制度や社内に障がい者向けの相談窓口の設置などを実施しています。
なお、国でも障がい者雇用促進は喫緊の課題としており、障害者雇用促進法で企業に対して雇用する社員の2.3%*に相当する障がい者の雇用の義務付けや、助成金による支援をしています。
*参考:厚生労働省|事業主の方へ|障害者雇用のルール|1.障害者雇用率制度
【3】外国籍人材の雇用促進
ダイバーシティ&インクルージョンの一つである外国籍人材の雇用促進は、労働力の確保に加えてビジネスのグローバル化に対応するためにも重要です。グローバル化したニーズに応えるには、日本的な慣習に囚われない視点が求められます。一方で、文化が異なり、外国籍の人材と共に働くことに慣れていない日本企業で、外国籍人材に活躍してもらうのは簡単ではありません。外国籍人材の社員が安心して就労できるように職場環境の整備や社会生活上の適切な支援が必要です。企業によっては、優秀な外国籍人材と出会うために、海外の就活イベントに参加するケースもあります。
【4】シニア層の活用
シニア層の活用もダイバーシティ&インクルージョンの取り組みの一つです。なかには、スキルや経験を豊富に持っている人材もいて、人手不足の解消はもちろん、新人社員の教育への貢献も期待できます。企業によっては、雇用していた社員に継続して働いてもらえるよう、再雇用制度の整備や定年制度の廃止などの取り組みを実施しています。
ちなみに、2021年4月に施行された改正高齢者雇用安定法では、65歳までの雇用確保が義務、65歳から70歳までの雇用確保が努力義務と定められました。国の政策としても、シニア層の積極的な活用が推進されていることが分かります。
【5】LGBTQへの配慮
性的マイノリティであるLGBTQへの配慮もダイバーシティ&インクルージョンでは欠かせません。社員同士で多様な価値観を認め合っている、尊重される企業では、ビジネスの競争力も高くなりやすいといえます。そのため、LGBTQといったマイノリティを受容することは、グローバル化し高い競争力が求められる近年のビジネス環境では重要な要素です。
これまでの日本企業では、そもそも性的マイノリティに対する理解が乏しいケースが多く、雇用を促進する前にLGBTQといったマイノリティへの理解を深めるための取り組みが必要です。こういった理解がない職場だと、当事者は安心して働けず、場合によっては退職する可能性があります。企業によっては、LGBTQの差別禁止を社内規定に明記したり、理解促進のためのセミナーやイベントなどを実施したりしています。
ダイバーシティ&インクルージョンの課題と対処法
ダイバーシティ&インクルージョンの課題として、「多様な人材が働きやすい環境が整っていない」「既存社員から受け入れられない」の2つが挙げられます。ここでは、それぞれの課題と対処法を紹介します。
多様な人材が働きやすい環境が整っていない
日本の企業ではダイバーシティ&インクルージョンの推進を阻害する要因として、環境が整っていないケースが挙げられます。以降で、ダイバーシティ&インクルージョンの実現に必要な環境を紹介します。
制度の整備
ダイバーシティ&インクルージョンを推進するためには、評価や働き方の制度を多様な人材に受け入れられるように整備する必要があります。たとえば、評価制度のケースでは、個人の能力やスキル、貢献度を軸にする、といったことです。年齢や勤続年数に応じて評価が上がる年功序列制度だと、外国人社員にとっては不満の原因になりかねません。評価制度を見直し、昇給・昇進基準が明確になればモチベーションの維持や人材の定着などの効果が期待できます。
ほかにも働き方に関する制度では、テレワーク制度や時間単位有給休暇制度の導入などの多様な働き方につながる制度の整備も大切です。
職場環境づくり
ダイバーシティ&インクルージョンの推進には、多様な人材にとって働きやすい職場環境づくりも重要です。働きやすい職場環境が整備されれば、人材の定着につながります。カシオが実施しているメニュー表記の工夫やお祈り部屋の設置は良い例です。他にも、障がいを持つ社員やシニア層が利用しやすいようにオフィスをバリアフリー化する、小さなお子さんがいる社員が子育てしながら働けるよう、保育所をオフィスに併設するなどの取り組みをしている企業もあります。
コミュニケーション方法の工夫
ダイバーシティ&インクルージョンでは、国籍や年齢など幅広い人材を受け入れるため、コミュニケーションに食い違いが生じやすく、コミュニケーション方法の工夫が必要です。企業では、外国人社員との言語の壁を解消するため、各部署に外国語を話せる人材を配置したり、障がいを持つ社員には、障がいの種類や程度に応じて対応してもらう業務や教え方を工夫するといった取り組みを実施しています。コミュニケーションが活発になると、生産性の向上や社員満足度の向上などが期待できます。
既存社員から受け入れられない
ダイバーシティ&インクルージョンの課題には、多様な人材が既存社員に受け入れられないことも挙げられます。既存社員のなかには従来の企業文化から脱せない人や、無意識のうちに偏見を持った言動を取る人もいるため、タイバーシティ&インクルージョンの必要性や推進によるメリットを理解してもらう取り組みが必要です。
既存社員が多様な人材を受け入れるためには、研修を実施しダイバーシティ&インクルージョンの理解を深めるのが効果的です。研修には社員だけでなく経営陣も参加すると、会社として本気で取り組む姿勢を示せるので社員の意識変容が期待できます。
ダイバーシティ&インクルージョンの取り組みにおけるポイント3つ
ダイバーシティ&インクルージョンを成功させるには、ポイントを押さえることが重要です。ここでは、ダイバーシティ&インクルージョンの取り組みにおけるポイントを次のとおり解説します。
- 【1】PDCAを回す
- 【2】数字達成だけを求めない
- 【3】多様な人材が働きやすい環境の整備
【1】PDCAを回す
ダイバーシティ&インクルージョンは、すぐに成果が上げられるものではありません。
「計画→実行→評価→改善」のPDCAサイクルを回すことで、取り組みの実効性を高め、継続的な改善をすることが成功のカギとなります。これを行わないと、目的を達成することは困難です。目的を達成するために、「取り組みがなぜ上手く行かなかったのか」など定期的なモニタリングを実施し、「どのように改善すべきか」など、必ず見直しを行いましょう。
【2】数字達成だけを求めない
ダイバーシティ&インクルージョン推進において、「女性管理職比率や障がい者雇用率の〇〇%達成」など、数値目標を立てることもあるでしょう。
こうした数値達成だけを追い求め、多様な人材を受け入れるための環境整備がおざなりになってしまっては、ダイバーシティ&インクルージョンを成功させることはできません。数値目標達成のみに注力するのではなく、「多様な人材を受け入れるための取り組み」をセットで取り組むことがポイントです。
【3】多様な人材が働きやすい環境の整備
多様な人材を受け入れるうえでは、人材の多様性に対応した環境整備をすることが重要ですが、それだけではありません。既存社員に不公平感が生まれないよう、全ての社員が働きやすい環境を整えることで、育児や介護をしている社員や、障がいを持つ社員などが、周囲に気兼ねすることなく働くことが可能です。特定の集団だけに環境を整えるのではなく、全社員を対象に環境を整えることで、ハラスメント防止などの効果も期待できます。
企業でのダイバーシティ&インクルージョン事例
日本ではさまざまな企業がダイバーシティ&インクルージョンに取り組んでいます。ここでは企業が実施している事例を紹介します。
女性リーダーを増やす活動|日本IBM
日本IBMでは、1998年よりリーダーポジションで活躍する女性を増やすことを目的としたJapan Women’s Council(JWC)という独自の活動をしています。JWCでは主に働き方改革に関する提言を行っています。社内で結成されたJWCの提言によって、以下のような人事制度が導入され女性が働きやすい職場が整備されています。
- 育児・介護との両立を支援する在宅勤務制度
- キャリアビジョンを描くためのメンター制度
- 1ヵ月労働時間を6割、8割にできる短時間勤務制度
- コアタイムなしのフレックス短時間勤務制度
- 本社内に保育所を開設
さらに女性社員や管理職、課長級以上の割合を増やすために、継続的なリーダーシップ開発研修や若手女性社員向けのキャリアについて考えるワークショップの実施などを行っています。
1店舗1人以上の障がい者を雇用|ファーストリテイリンググループ
ファーストリテイリンググループでは、1店舗1人以上の障がい者雇用の実施と障がい者雇用研修に取り組んでおり、2020年の国内の障がい者雇用率は4.71%と日本の法定雇用率の2.3%を大きく上回っています。1店舗1人以上の障がい者雇用については、2012年度以降はほぼ達成しています。また、店長や社員を対象として障がい者雇用に関する研修を実施し、障がいを持つ社員のパフォーマンス向上を目指しています。
外国人社員が働きやすい環境づくり|カシオ
カシオでは、外国人社員が入社後に長く働き続けられるように、外国人社員の声を聞いたうえで以下の取り組みを実施しています。
- 外国人社員が母国に帰るための特別休暇を3年に1度のペースで付与
- お祈りするための個室を社内に整備
- 外国人社員の日本語能力向上支援
- 食堂メニューへの英語表記
- 宗教や食文化に対応するため、食堂メニューに使用している肉のイラストを記載
これらの取り組みによって外国人社員が抱える宗教や言葉の壁などの不安を解消でき、早期の離職や労働意欲低下を回避することにつながっています。また、外国人社員の個々の能力を発揮しやすく、成果にも結びついています。
定年年齢を引き上げスキル継承|大和ハウスグループ
大和ハウスグループでは、やる気のあるシニア層が活躍できる環境を整備し、社員の育成や人脈・スキルの継承などを行いさらなる発展を目指しています。高齢者雇用安定法の改正に伴い、2013年度から定年年齢を65歳に引き上げました。さらに2015年度からは65歳での定年後も再雇用するアクティブ・エイジング制度を創設しています。
LGBTQに関する社内外の活動|JAL
JALではLGBTQの社員に配慮して、法律上の結婚をしている社員に適用する制度を同性パートナーにも適用できるようにしています。また、LGBTQの理解促進のために社内研修の実施はもちろん、社外に向けても理解促進のためのセミナー・イベントを実施しています。2019年にはJAL LGBT ALLYチャーター便を運行し、社会のLGBTQの理解促進に貢献したと、任意団体「work with Pride」から高い評価を受けています。
仕事と家庭の両立を支援|LIXIL
LIXILでは、社員が能力を発揮していきいきと働けるように、仕事と家庭の両立を支援する制度の充実や組織風土づくりのために以下の取り組みを実施しています。
- テレワーク制度
- 時間単位有給休暇
- 出産や育児、介護、配偶者の転勤などで退職した社員の再雇用
- 延長保育料補助や認可外保育施設の利用料補助
- 男性社員向けの出産・育児休暇
特に男性社員向けの出産・育児休暇の取り組みは、日数を拡大し取得方法を柔軟にしたことで利用者が増加しました。
ダイバーシティや多様な人材の管理職登用|資生堂
資生堂では、企業理念を実現するため、新しい価値の創造に向けてダイバーシティ&インクルージョンを次のとおり推進しています。
- 女性の活躍支援
- 女性リーダー育成
- LGBTに関する取り組み
- 障がいある社員の活躍
- 外国籍の社員の活躍
- 定年後再雇用制度
- 有期契約社員の雇用
- 派遣社員の就労
なお、東京証券取引所が公表するコーポレートガバナンスのガイドライン「コーポレートガバナンス・コード」では、人材戦略の重要性に鑑み、女性や外国人、中途採用者の管理職への登用など、中核人材の多様性の確保に向けた考え方と目標・状況を開示することが求められています。同社では、多様性を認め合い「個の力の強化」「人の力の最大化」によって強い会社づくりを推進すべく、多様な人材の管理職登用に取り組んでいます。女性・外国人・中途採用者の状況は、「社会データ」にて開示しています。
まとめ
ダイバーシティ&インクルージョンとは、組織において多様性を重視し個々の違いを受け入れたうえで、組織の活動にその違いを生かしていこうという考え方です。お互いを受け入れながら成長し、新たなサービスや価値を創造できるうえ、働き手不足や消費者のニーズの多様化などに対応できると注目されています。ただし、ダイバーシティ&インクル―ジョンを社内に浸透させるためには、職場環境整備や社内の理解促進などが必要です。
「障がい者・外国人の採用」というように、シーンごとに関連する法律と違法となるケース・罰則内容をまとめた資料がございます。「知らぬ間に法律違反になっていた!」とならないよう、採用活動時のチェックにもお役立てください。
無料ダウンロード
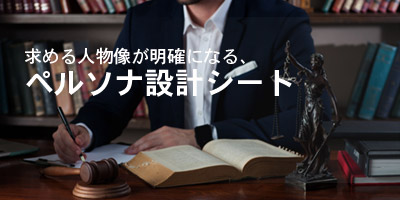
無料ダウンロード
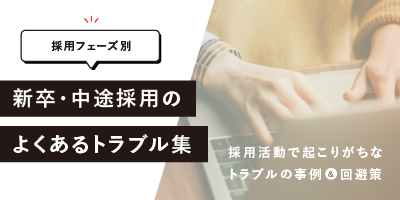
新卒・中途採用のよくあるトラブル集
新卒・中途採用でありがちなトラブルを「募集時」「選考時」「内定後」など、フェーズごとに紹介。「募集時」「選考時」「内定後」など、フェーズごとの起こり得るトラブルと回避策をまとめています。採用活動の資料としてお役立てください。
セミナー情報

あわせて読みたい