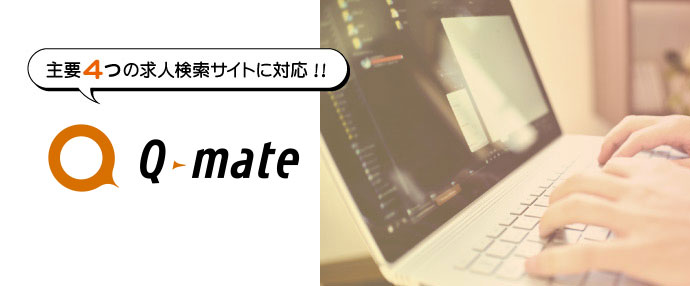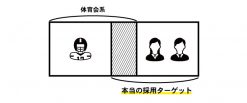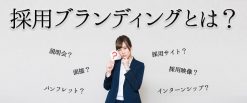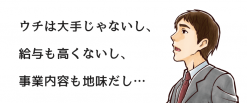採用パンフレットとは?
採用パンフレットとは、企業が新卒や中途採用での求職者に対し、自社の魅力や情報を伝えるための重要なツールです。このパンフレットは、リクルートパンフレットや入社案内などと呼ばれることもあります。
チラシやパンフレットなど、多様な媒体がありますが、近年ではデジタル化も進んでおり、PDF形式などでスマートフォンやパソコンからも閲覧可能なものもあります。さらに、パンフレット内にQRコードを配置し、企業のウェブサイトや採用ページにリンクする方法も増えています。
採用パンフレットには、企業の特徴や働く魅力、福利厚生などの情報が盛り込まれており、転職フェアや合同説明会、内定者フォローのタイミングなどで配布されることが一般的です。
採用パンフレットの役割とは?
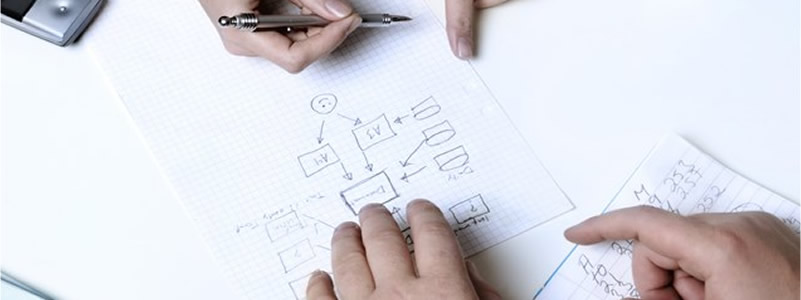
採用パンフレットは求職者にアプローチするためのツールとして合同企業説明会や会社説明会で配られることが多く、主に3つの役割があります。
【1】自社についての理解促進
採用パンフレットには、求職者に自社の事業内容の理解を促す役割があります。事業内容を紹介するための会社案内やパンフレットを用意している企業は多いですが、そのほとんどはクライアントに配ることを前提として作られています。そのため、業界に詳しくない求職者、特に新卒者にとっては内容が理解できないこともあります。採用パンフレットでは、会社案内とは違った表現を用いて、知識がない人でも事業内容を理解できるような工夫を施す必要があります。
【2】自社への共感を醸成
求職者の中でも社会人経験がない新卒者は、業種や職種によっては働くイメージがまったくわかないことがあります。しかし、業種や職種についてわかりやすく綴られ、社内の雰囲気が伝わる採用パンフレットがあれば、入社後の自分を想像しやすくなり、企業に共感や親しみを持ってもらうきっかけにもなります。
【3】求職者のギモンを解決
採用パンフレットには、求職者に寄り添った形で、入社にあたっての疑問や不安を解消する役割もあります。業務内容や福利厚生に関するQ&Aや先輩社員へのインタビューがこれに当たり、求職者目線で見たときにわかりやすい内容にすることが求められます。
採用パンフレット作成のメリット
採用パンフレットを採用することは、企業側、求職者側の双方にとってメリットがあります。
企業側のメリット
採用パンフレットを作成することによる企業側のメリットは、以下のような要素があります。
会社の認知度拡大が期待できる
合同説明会やインターン実施時に採用パンフレットを配布することで、貴社の認知度を高めることができます。特に、目を引く表紙や興味を引く内容を工夫することで、求職者の注目を集めやすくなります。
求職者の入社意欲を向上できる
魅力的な採用パンフレットを作成することで、求職者の興味を引くことができます。興味を持ってもらった上でパンフレット内の企業情報を読んでもらえれば、求職者の入社意欲を向上させる効果が期待できます。
リマインド効果がある
採用パンフレットは手元に残るため、例えば選考に進んだタイミングや最終面接の後など、後日改めて読み返される可能性があります。これにより、短期的な応募数の増加だけでなく中長期的な応募獲得のきっかけとなる可能性があります。
入社後の早期離職を防ぐことができる
パンフレットを通じて企業の情報を詳しく知ることで、入社前の期待と実際の業務内容とのギャップを減らすことができるため、入社後の定着率を向上させることにも役立ちます。
求職者側のメリット
採用パンフレットを受け取ることにより、求職者側にも様々なメリットがあります。
比較的容易に企業理解ができる
採用パンフレットにはその企業・職種に関する情報が整理されて記載されているため、比較的容易に企業理解をすることが可能です。
特に紙媒体で作成された採用パンフレットの場合、WEBサイトと異なり別のページに飛んだり何度もスクロールする必要がありません。そのため、その視認性の高さから、よりスムーズな企業理解が可能となります。
後から確認ができる
採用パンフレットは後から確認ができるため、入社前や選考段階での情報確認に役立ちます。情報を手元に置いておくことで、より慎重な企業選びが可能となります。
疑問解消に役立つ
採用パンフレットにはその企業に関する詳細な情報が記載されているため、入社前の疑問や不安を解消するのに役立ちます。職種ごとの詳細や研修内容、先輩社員へのインタビューやQ&Aなどがこれに当たります。
他社との比較検討がしやすい
複数の企業の採用パンフレットを比較することで、自身に最適な企業を見つけることができます。採用パンフレットは企業ごとの特徴や魅力が凝縮されているため、比較検討が容易になります。
採用パンフレット作成のデメリットや注意点
採用パンフレットを作成する際には、いくつかのデメリットや注意点が存在します。
制作コストや印刷コストがかかる
採用パンフレットを作成する際には、制作費や印刷費用がかかるというデメリットがあります。デザインや素材の選択によって相場となる費用は変動しますが、ページ数やデザインの複雑さによっては、数十万円から100万円以上の費用がかかることもあります。
さらに、紙として提供する場合は、制作費用だけでなく印刷代も必要です。配布範囲や数量に応じて印刷費用も増加することに留意が必要です。また、紙媒体の場合、効果の測定が難しく、費用対効果の判断が難しい面も考慮しておく必要があります。
対面で渡す機会が必要
採用パンフレットは主に会社説明会などの対面イベントで配布されることが多いため、配布する機会が限られます。また、近年ではオンラインでの会社説明会が増えており、対面で配布する機会が減少しています。そのため、対面で渡す機会が限られる場合は、効果的な配布方法を検討する必要があります。
情報更新にコストがかかる
採用パンフレットは印刷物であり、情報の更新が難しいという点もデメリットです。一度印刷してしまったパンフレットは、画像の差し替えやテキストの修正が困難です。このため、企業情報の変更や新たな情報の追加があった場合、再度制作・印刷する必要があり、これにはコストがかかります。
採用パンフレットを構成する内容
採用パンフレットは以下の内容で構成されることが多いです。ただし、これらを網羅することは必須ではなく、採用フロー全体のなかで採用パンフレットに持たせる役割によっては、要素を絞り込んでもかまいません。
表紙・裏表紙
採用パンフレットの顔となり、自社のイメージに直結する部分です。どんなイメージを与えたいかによってデザインが変わります。インパクトを持たせて他社との差別化を図るために、 丸型にしたり自社製品の形状に切り抜くなどの特別な見た目にしたりするのも丸型にしたり自社製品の形状に切り抜くなどの特別な見た目にしたりするのもひとつの方法です。
採用キャッチコピー
こちらも表紙同様、自社のイメージに直結します。求職者の印象に残るのは、簡潔でインパクトがあるキャッチコピーです。長くても20文字程度に抑えるのが良いでしょう。自社が大切にしているスタンスをもとに考えるのがスムーズです。複数の単語を並べただけのシンプルなパターンや、疑問・逆説・比較などの表現で求職者の興味を惹くパターンもあります。
創業理念・沿革
自社の歴史について説明します。ただ単にこれまでの出来事を並べるのではなく、自社にとってのターニングポイントをピックアップするといった工夫をし、ストーリー性を持たせると求職者の理解につながります。
事業説明
自社の事業について説明します。求職者の理解を深めるために、できるだけわかりやすい表現にすることがポイントです。業界特有の表現や専門用語を使う場合は知識のない求職者でも理解できるような補足などを入れましょう。イラストや漫画を使って説明するとよりわかりやすく、親しみをもたらします。
採用メッセージ
求職者に対するメッセージです。一般的には「簡単な事業内容説明→企業としての今後やスタンス→求職者に期待すること」という流れで構成されることが多いです。求職者に伝えたいことをコンパクトにまとめて、500文字前後に抑えます。
先輩社員の声
実際に働いている社員の声は、求職者が最も知りたい部分のひとつです。新卒1年目の社員、中途社員、子育て中の女性社員など、複数の立場からの声を掲載すると、より社内の雰囲気が伝わります。ただし、自社の良い面ばかりをアピールすると、求職者は「こんな都合の良い話があるはずはない」「信ぴょう性に欠ける」と感じ、逆効果になることもあります。ネガティブにならないように配慮しつつ、リアルな現場の声を届けるために、「業務上でこんな苦労があったが、こうして乗り越えた」といった内容のエピソードを入れると良いでしょう。
募集要項
募集要項には正確さはもちろん、実際の働き方をイメージできるような具体性も必要です。例えば、募集職種の欄は「〇〇の提案営業」だけで終わらせずに、営業手段や扱う商材などについても明確に説明します。
福利厚生・教育体制
就職先を選ぶ際に、福利厚生や教育体制を重要視する求職者も少なくありません。内容の羅列だけではイメージが湧きにくいので、実際に社員がどのように活用しているかを紹介するのも良いでしょう。
社風・社外活動
自社らしさをアピールできる部分です。説明だけではわかりにくいので、写真などを使ってより雰囲気が伝わるようにしましょう。
採用パンフレット制作の5ステップ
採用パンフレット制作の作り方についてご紹介します。
【1】採用戦略・ターゲットの策定
採用戦略を立て、採用ターゲットを具体的にしていきます。その内容を採用担当者だけでなく、社内でしっかりと共有することによって、採用パンフレット制作はもちろん、採用活動全体がスムーズに進みます。
【2】パンフレットの目的を明確化
採用パンフレットを使ってどんな目的を果たしたいか、どのようなことを伝えたいかについて考えていきます。これをもとに採用パンフレットのコンテンツを決めます。
【3】制作スケジュールの決定
採用パンフレットのコンテンツが明確になったら、制作スケジュールを決めていきます。基本的には使用する3カ月前から準備に入ります。コンテンツによっては、役員や社員へのインタビューや写真撮影が必要となるので、そちらのスケジュールも調整しておきましょう。
【4】制作依頼先の選定
採用パンフレットの制作は、多くの場合は制作会社に依頼する必要があります。クリエイターが在籍しているデザイン会社などクリエイターが在籍しているデザイン会社など、自社で制作体制が整っている場合はそちらと相談しましょう。
制作会社を選ぶ際は、採用関連の制作を得意とし、採用や人事の知識を持っているのかどうかに着目してください。採用パンフレットと一般的なパンフレットとでは、注意すべきポイントが異なるためです。
採用コンサルティング会社がコンサルティングの一環として採用パンフレットの制作を行っている場合もあります。
【5】制作開始
採用パンフレットの制作を進めていきます。理想の採用パンフレットが作れるように、制作側としっかりイメージをすり合わせておきましょう。
採用パンフレット作成のポイント
採用パンフレットを作成する際には、以下のポイントに留意することが重要です。
いつどのように活用するのかを決めておく
採用パンフレットは制作に数カ月間を要します。そのため、事前に活用のタイミングを決めておき、計画的に制作することが大切です。例えば、説明会で配布する、インターンでの自社の説明に用いるといった使い方が考えられます。
弊社クイックでは、採用戦略の立案を含めた採用の全体設計を行い、採用戦略に沿った採用パンフレットの作成を行っております。
以下の記事からさまざまな採用パンフレットの事例をご覧いただけますので、ご興味ございましたらぜひご覧くださいませ。
https://saiyo-salon.jp/creative/creative_tag/recruiting-pamphlet/
メッセージの明確化とターゲットの考慮
採用パンフレットは、相手に伝えたいメッセージを明確にし、ターゲットの興味やニーズに合わせて情報を選択することが肝要です。また、新卒採用の場合には、学生だけでなく、その家族や友人にも興味を持ってもらえるような内容を提供することが重要です。
一貫性の確保とブランディング
採用パンフレットの内容は、一貫性を持たせることが重要です。会社のビジョンや企業理念を伝え、ブランディングに力を入れることで、読み手に強い印象を残すことができます。デザインや表現方法にも統一感を持たせることが大切です。
共有欲を喚起するコンテンツとSNS連携
興味深い情報を提供し、読み手の共有欲を刺激することも重要です。また、SNSとの連携を図り、読み手が情報を拡散しやすいような工夫をすることで、パンフレットの効果を高めることができます。
不安解消と安心感の提供
採用に関する不安を解消し、安心感を与えることも大切です。実際の社員の生活やリラックスできる環境などを写真や文章で伝え、読み手に会社の魅力を実感させることが重要です。
デザイン性の追求と第一印象の重要性
採用パンフレットのデザインは第一印象を左右します。表紙や中身のデザインにこだわり、会社のイメージや採用戦略に合った魅力的なデザインを追求しましょう。また、写真の活用や福利厚生の明確な説明も忘れずに行いましょう。
写真を多用する
写真を多用することが重要です。写真は会社の雰囲気や文化を伝える重要な手段であり、文字だけでは伝えきれない情報を補完します。社員の日常やリラックスした雰囲気を写真によって表現することで、求職者に安心感を与えることができます。
面白さ・遊び心も大切
採用パンフレットのデザインやコンテンツに面白さや遊び心を取り入れれば、親しみやすさや前衛的な姿勢をアピールすることにつながります。求職者が「応募したい!」と感じるようなパンフレットは何かという基準をもとに工夫を施しましょう。
まとめ
本記事では、採用パンフレットの概要や作成するメリット・デメリット、作成手順をご紹介しました。
採用パンフレットをうまく活用することで認知度の拡大や採用ブランディング、応募数の増加などの効果が期待できます。
採用パンフレットの企画・制作にお悩みの企業様はぜひ、お問い合わせください。
【関連ページ】
⇒パンフレット・リーフレット等印刷物・ブース装飾:サービス紹介ページ
無料ダウンロード
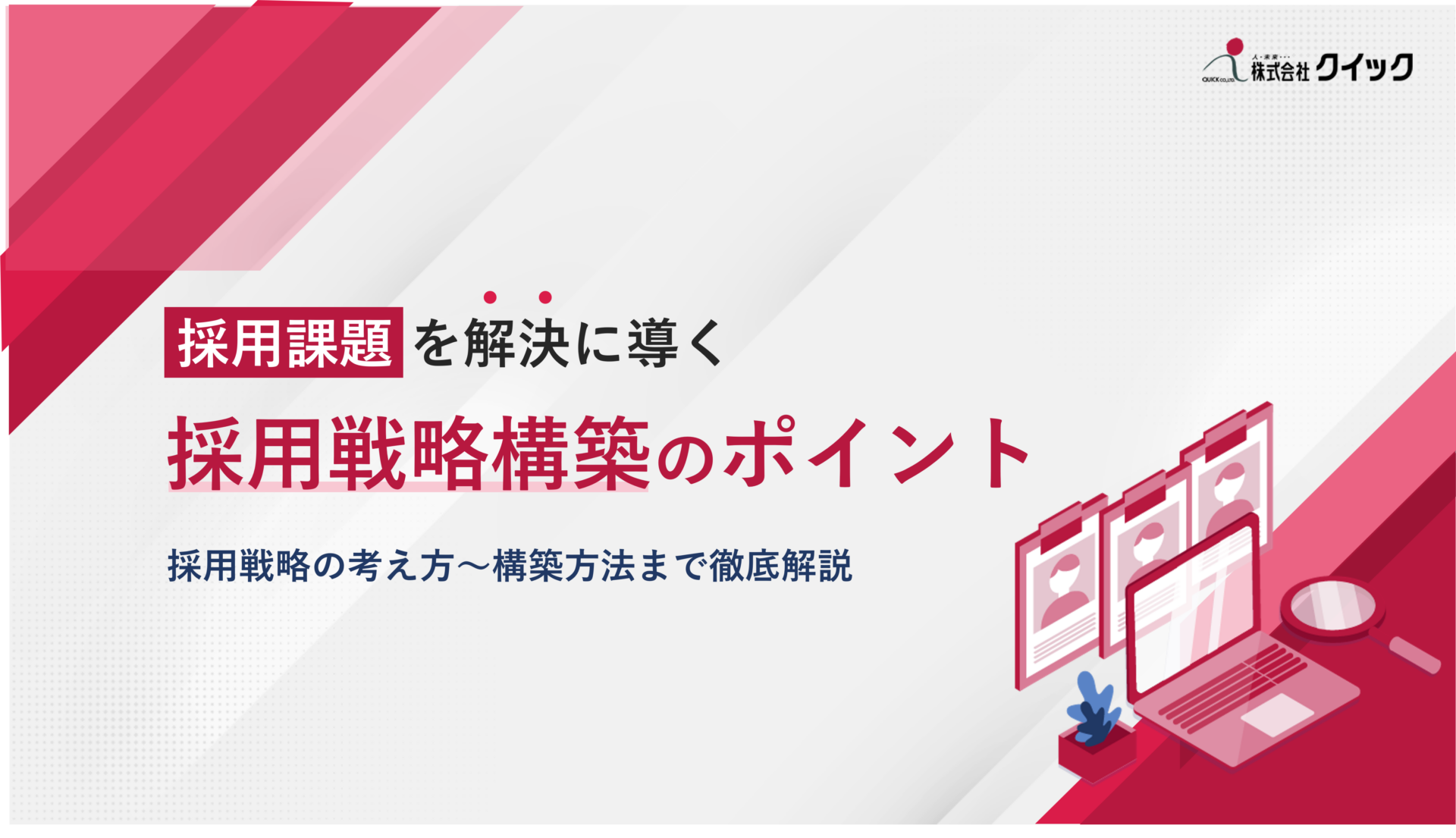
採用課題を解決に導く採用戦略構築のポイント
採用活動においても、パフォーマンスの要となるのは「戦略」の設計です。 コンサルティングサービス「採活力」は、貴社に最適な採用コミュニケーションを設計し、採用活動を成功へと導きます。
セミナー情報

あわせて読みたい