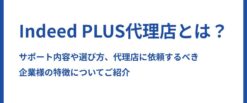外国人材の雇用動向と受け入れ拡大の背景
厚生労働省が発表した『「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)』によると、国内の外国人材数は約230万人と過去最多を更新しており、外国人採用は増加傾向にあることが分かります。
外国人採用が増加している背景として、以下3つの理由が主に挙げられます。
1つ目は、労働力の確保です。少子高齢化が進む日本において、必要な労働力を確保するために外国人採用に着目する企業様が増えています。特にサービス業や製造業を中心に、外国人材が欠かせない存在になりつつあります。
2つ目に、法整備の進行です。出入国管理及び難民認定法の改正*や特定技能制度の新設**など、外国人材をより受け入れやすくするための法制度の整備が進んでいます。その結果、以前よりも幅広い職種で外国人材が就労できるようになり、企業にとって外国人材の採用がより身近な手段として注目を集めています。
3つ目が、企業力の向上です。グローバル化が進む中、多国籍な人材を迎え入れることで企業の国際競争力や生産性の向上を期待する動きも増えてきています。
このように、日本の労働人口の減少や法制度の刷新、企業力向上という観点から、外国人材の採用は注目を集めています。
*令和6年入管法等改正法について | 出入国在留管理庁
**特定技能制度 | 出入国在留管理庁
外国人採用におけるメリットと課題
外国人採用のメリット
人材不足の解消
国内の労働人口が減少する中、外国人材は貴重な労働力となります。特に、若年層の人材確保が困難な製造業や介護、外食産業などでは、即戦力として活躍するケースも増えています。
組織の多様性向上とイノベーション促進
異なる文化的背景を持つ人材が加わることで、社内に新たな視点や価値観が生まれます。これにより、これまでになかったアイデアが生まれやすくなるほか、グローバル展開を見据えた企業体制の構築にも貢献しています。
海外ビジネス展開の足がかり
外国人材の持つ母国とのネットワークや語学力を活かすことで、海外市場へのアプローチにも寄与します。現地の商習慣や文化理解に基づいた事業展開を行うことができるため、国際ビジネスの橋渡し役として期待されています。特に、企業の進出先と人材の国籍が一致するケースでは大きな相乗効果が現れる可能性があります。
外国人採用の課題や注意点
コミュニケーションや業務理解に対するギャップ
日本語能力に個人差があるため、業務指示やマニュアルの理解に時間がかかるケースがあります。また、報連相(報告・連絡・相談)や暗黙の了解など、日本特有の職場文化に馴染むまでに一定の時間が必要となります。そのため、初期の教育やフォロー体制の整備に一定の工数がかかる可能性があります。
在留資格や労務管理の複雑さ
外国人材を受け入れる企業様にとって、在留資格の取得や更新に関する法的な知識は不可欠です。特に、在留資格の種類によっては、従事できる業務内容や就労時間に制限が設けられているケースもあり、一般的な労務管理と比べて、より高い専門性が求められます。
たとえば、資格外活動の許可が必要となる場合や、週28時間以内の就労制限がある在留資格など、雇用形態によって遵守すべきルールは多岐にわたります。これらの条件を正確に把握・管理しないまま雇用を進めると、法的なリスクを伴う恐れもあるため、慎重な対応をする必要があります。
外国人材を採用するまでの手続きとパターン
外国人採用には、海外からの招聘や中途採用、留学生の新卒採用など、さまざまなパターンと手続きがあります。
特に、海外在住の人材を招聘する場合と日本国内に既に滞在・就労している外国人材を採用する場合では、必要となる手続きが異なります。企業としては、採用したい職種やスキルレベルに応じて最適なパターンを選定し、スケジュールを立てることが重要です。この際、海外からの人材受け入れには時間がかかる場合が多いので、早めに準備を開始する必要があります。
また、外国人留学生の新卒採用では、学校卒業後に就労可能な資格への切り替えをサポートするなど、企業側の積極的な対応が大切です。彼らにとっては初めてのフルタイム就職となるため、適切な説明とフォローをすることで、安心して社会人生活をスタートしていただけます。
海外から招聘する場合の流れ
まずは日本の入国管理局に対し、在留資格認定証明書の交付申請を行い、受理後には外国の日本大使館または領事館で査証申請を行う流れとなります。書類準備には時間と手間がかかるため、計画的な進行が大切です。
新規にビザを取得する場合、企業からの雇用契約書や職務内容を示す資料なども提出資料として求められます。これらは取得資格の妥当性を審査する上で重要な根拠となるため、誤字脱字を含めたミスがないよう注意が必要です。
入国後は空港などで在留カードを受け取り、住民登録や社会保険の加入手続きへと移ります。採用された方は異国の地で慣れない手続きを行うことになるため、積極的にサポートし、早期に職場適応を促す環境づくりを行うことが重要です。
日本国内で就労中の外国人材を中途採用する場合
すでに他社で働いている外国人材を中途採用する場合は、当該の方が保持している在留資格で新しい環境でも業務を続けられるかどうかが焦点になります。業務内容が変わる場合は、条件等に応じて在留資格の変更や更新手続きを行う必要があります。
転職したことによる資格変更の手続きは、基本的には転職者自身が実施するものの、企業側が積極的に協力することでスムーズに進みやすくなります。書類の準備や生活面でのサポートなど、細やかな配慮を行うことで企業と求職者の方の信頼関係を醸成することができます。
また、中途採用では前職での就労実績や雇用形態が審査のポイントになることもあります。正当な理由で転職をすることが明確になっているか、活動範囲が適切かなどを、企業側でも確認することが推奨されています。
外国人留学生を新卒採用する場合
日本で学ぶ外国人留学生を新卒として採用する際は、まず卒業見込みであることを前提に、就労可能な在留資格への切り替えを検討します。留学ビザから就労ビザへの変更に際しては、内定証明や雇用条件の提出が必要となることが多いです。
留学生にとって日本の就職活動の流れは分かりづらい場合もあるため、丁寧な説明やサポートを行うことで、企業に対する信頼感が高まります。
卒業後の在留資格変更が認められるまでは、アルバイトなどの範囲でしか働けない期間が生じる場合があります。その間の生活費補助や、初回の給与支給タイミングなどについても、事前に両者でよく相談しておくことがおすすめです。
在留資格による就労条件の違い
ここでは、それぞれの在留資格と、就労条件についてご紹介します。その人材が保有する在留資格によって就労可能な業務や時間が異なるため、正しく理解する必要があります。
例えば大学卒業者が多い「技術・人文知識・国際業務」資格では、翻訳や通訳業務、エンジニア業務など専門的な分野での就労が可能になります。
一方、「特定技能」や「技能実習」などは、特定の業種や作業内容に限定された資格となるため、企業側が対象業務を明確化しないと不適切な配置を招く恐れがあります。
また、日本人の配偶者等や永住者など、就労に制限がない在留資格を持つ外国人材は、幅広い業務に対応できます。ただし、資格が変わるたびに就労条件も変わるため、雇用管理のためには常に最新情報を取り入れる体制の構築が必要です。
それぞれの在留資格の詳細については、こちらの「在留資格一覧表 | 出入国在留管理庁」をご参照ください。
就労制限がない在留資格
永住者や日本人の配偶者等、定住者などは基本的に職種・業種を問わずに働くことができます。このような資格を持つ外国人材は、日本国内で長期的に生活している場合が多く、日本語のコミュニケーションに長けているケースも少なくありません。
ただし、就労制限がないとはいえ、在留資格の期限管理や延長手続きは必要になる場合があるため、本人任せにせず企業側も可能な限りのバックアップをすることが望ましいです。
就労制限がある在留資格
技術・人文知識・国際業務のように、認められた専門分野に限定して就労が認められる資格があります。例えば語学スキルを活かす通訳・翻訳業務や、システムエンジニア、または海外営業などがその例です。
制限ありの資格を持つ外国人材を雇用する際には、想定している職務が資格の活動範囲内であるかどうかを確認する必要があります。特に、一般事務や接客などの業務を任せる場合は、資格外活動に該当しないか注意が必要です。
企業の事情で職務内容が変更になる可能性がある場合でも、法令に抵触しないよう迅速に在留資格変更や追加許可の取得に対応する必要があります。
就労不可の在留資格
就労を目的としていない在留資格を持つ外国人材は、原則として日本国内での就労が認められていません。これらの資格で在留している外国人材を無許可で働かせた場合、企業側が不法就労助長罪に問われる可能性があるため、十分な注意が必要です。
代表的な就労不可の在留資格には、「短期滞在」「留学」「研修」「文化活動」「家族滞在」などがあります。たとえば「短期滞在」は観光や親族訪問、商談などを目的とした資格であり、報酬を伴う就労は一切認められていません。ただ、「留学」や「家族滞在」は一部の条件下で「資格外活動許可」を取得すれば、週28時間以内など制限付きでのアルバイトが可能になることもあるため、確認が必要です。具体的な要件や申込書のダウンロードは、下記リンクよりご確認いただけます。
特定技能制度と登録支援機関の活用
2019年に新たに設けられた特定技能制度を利用することで、より幅広い外国人材の受け入れが可能となります。
特定技能制度は、特定の業種で一定の技能水準や日本語能力を満たした外国人材を受け入れる仕組みです。16業種が対象となっており、人手不足が深刻な分野で働き手を確保するための政策として導入されました。
特定技能の外国人材を受け入れる企業は、生活支援や日本語学習支援などを含む支援計画の策定と実施が法的に義務付けられています。もし、これらの支援を自社で適切に行うことができない場合には、法務省に登録された登録支援機関と連携する必要があります。これらの支援体制が不十分だと判断された場合は在留資格の許可が下りないこともあるため、きちんと体制を準備しておくことが必要です。
また、特定技能1号と特定技能2号では在留期間や家族帯同の可否など条件が異なります。以下、それぞれの内容についてご紹介します。
特定技能1号・2号の違い
特定技能1号は、即戦力として一定の技能レベルが認められた外国人材を対象に、最長5年の在留が可能な資格です。ただし、原則として家族の帯同はできない点が特徴とされています。
一方で特定技能2号は、より高度な技能を身につけている外国人材が対象となります。2号の在留期間は上限がなく、家族帯同も認められる可能性があります。現段階では対象業種が限られていますが、将来的に拡充されるかが注目を集めています。
(現在は、介護、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業を除く11分野が対象)
出入国在留管理庁によるそれぞれの制度の説明は以下の通りです。
| 特定技能1号 | 特定技能2号 |
| ・特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動を行う ・技能試験と日本語試験に合格する必要あり(技能実習2号を良好に修了した場合は免除) ・所属機関または登録支援機関による支援の対象 ・原則、家族帯同は不可 ・在留できる期間は5年まで ・付与される在留期間は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) | ・特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動を行う ・特定技能1号より高度な技能試験に合格する必要があるほか、一定の実務経験が求められる ・所属機関または登録支援機関による支援の対象外 ・配偶者と子の帯同可能(「家族滞在」の在留資格を得る必要あり) ・在留期間の更新を受ければ上限なく滞在可能 ・付与される在留期間は3年、1年又は6月 |
※上記表は、受入れ機関の方 | 出入国在留管理庁を参考に作成
雇用時に必要な手続き
外国人材を正式に雇用するにあたっては、労働条件を明確に伝え、相手が納得したうえで労働条件通知書・雇用契約書の作成・提示を行うことが重要です。この際、言語サポートを用意することで契約内容の齟齬やトラブルを防ぎやすくなります。
労働条件通知書・雇用契約書の作成
労働条件通知書や雇用契約書には、賃金・就業時間・休日・勤務地など基本的な条件を明記し、外国人材にも理解しやすい形で提示することが不可欠です。可能であれば、母国語版の契約書や通訳サポートを用意することで、ミスコミュニケーションを防ぐことができます。
この際、口頭だけの説明に頼ると、言葉のニュアンスや理解の相違からトラブルに発展するケースがあり得ます。そのため、会社の服務規定や守秘義務なども明文化しておくことや、契約更新時や給与改定時などの重要な変更事項は書面で通知することにより、後々のトラブルを回避する対策が必要です。
社会保険・労働保険の加入手続き
日本の社会保険制度は、一定の就労条件を満たす労働者全員に、国籍を問わず適用されます。健康保険や厚生年金保険は法律上の要件を満たす従業員であれば加入義務があり、企業側には届け出の義務があるため、きちんと対応する必要があります。また、労災保険や雇用保険についても同様に、日本人と同じ基準で適用する必要があり、不当に加入を拒否するなどの行為は違法です。
保険料の計算や保険証の受け渡しなど、細かい手続きをスムーズに行うためには、総務部門や人事部門の担当者と連携し、マニュアルを整備しておくことをおすすめします。
保険の加入手続きに関する詳細は『外国人従業員を雇用したときの手続き|日本年金機構』をご参照ください。
外国人雇用状況届出書の届出
外国人材を採用した全ての事業主は、「外国人雇用状況届出書」を届出する義務があります。届出書には外国人材の氏名や在留資格、在留期間などを記載し、採用時だけでなく、離職した際にもハローワークに提出する必要があります。提出期限を守らなかったり虚偽の申告をしたりすると、30万円以下の罰金が科される可能性があるため注意が必要です。
労働基準法や労働安全衛生法への対応
外国人材も日本人従業員と同様に、労働基準法や労働安全衛生法の適用を受けます。そのため、試用期間を設ける場合にはその期間や条件を明確にし、公平かつ透明性のある運用を行う必要があります。また、健康診断は雇入れ時や定期的に実施することが法令で義務付けられています。日本の健康診断制度になじみの薄い方のために、事前に内容や受診方法を丁寧に案内することも重要です。
まとめ
外国人材の採用を行うことは、人手不足の解消や組織の多様性向上、海外ビジネス展開の足がかりとして非常に効果的です。一方で、在留資格による就労条件の違いや、コミュニケーション面での課題、複雑な手続きなど、企業が理解すべきポイントは多岐にわたります。
ここで重要なのは、外国人材の採用を単なる労働力確保の手段として捉えないことです。働き手が見つからない場合、職場環境や就労環境に課題がある場合もあります。中長期的に求職者から選ばれ続ける企業になるためには、国籍問わずさまざまな人材に魅力を感じてもらうための環境を整備することが大切です。
クイックでは、外国人材の採用に関するご支援を行っております。貴社のご状況に応じて適切なサービスやプランを選定、ご提案させていただくことが可能ですので、ご興味のある企業様はぜひ、お気軽にお問合せください。
また、外国人採用に関するセミナーも定期的に開催しております。詳細は下記リンクより御覧ください。
新常識!外国人採用3.0とは? ~在日東南アジア人20万人のネットワークと約600名の紹介実績を持つLivCo社が語る採用成功の法則~(無料)
あわせて読みたい